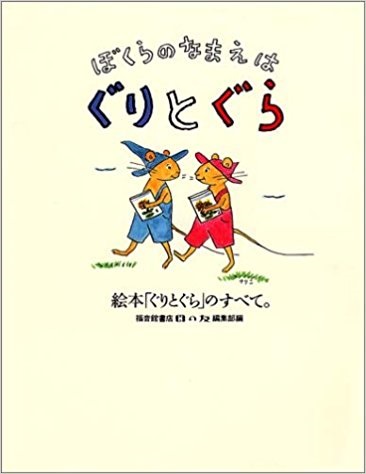2017年11月8日 発行
■食べ物への興味■
子どもの成長を後押しする幸せな時間
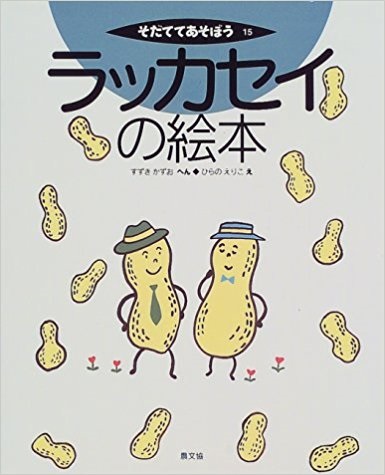
『ラッカセイの絵本』農文協
アメリカで定番のサンドイッチにピーナッツバター&ジェリーサンドイッチがある。パンに落花生ことピーナッツで作ったバターとフルーツのジェリー(ジャム)をぬって挟んだサンドイッチだ。日本のピーナッツバターは甘いので、それにジャムまでぬるなんて!と思うが、アメリカのピーナッツバターは甘くないので、ジャムの甘みがちょうどよくて美味しいサンドイッチになる。
アメリカではピーナッツバター&ジェリーサンドは、日本のおにぎりのように、ハイキングのお弁当やランチなどにごく普通に食べられるサンドイッチで、このサンドイッチの作り方を歌った英語の子どもの歌もある。その題名はサンドイッチの名前と同じで、Peanut Butter and Jellyだ。
ラボ・パーティでは、子どもたちとこの歌を、サンドイッチを作る様子がコミカルに表現されたダンスで楽しむ。この歌の歌詞やメロディーは色々なバージョンがあるようだが、私たちがいつも歌う歌詞の一部にはdig-em,dig-em,と土を掘る歌詞がある。
ピーナッツは日本語で落花生と書くことからもわかるように、花が咲いた後は土の中にもぐって実をつける植物だ。そこで、土を掘る振り付けで踊りながら、私は子どもたちに「ピーナッツは地面の中で実るんだよ」と説明するが、どの子も不思議な顔をしているだけでわかったのかどうなのか…。
仕方ないので、ホームセンターで見つけた落花生の苗を育てて、みのった実を掘らせたりしたこともあるが、子どもは「ふーん」という感じで、驚きも喜びもしない。どちらかというと、大人の方が驚いて感動していたりする。
*
今の子どもたちにとって食べ物は、加工されてきれいに包装され、封を空ければすぐに食べられる状態でお店に売られているもので、加工される前の素材がどういうものなのか、どのように育ってきたものなのかということには無関心なのだろう。
我が子だって、おままごとをしながら一番たくさん出てきたセリフは、「買ってこなくちゃ」で、育てるとか収穫するとか作るとか、耕作や調理に関わる言葉は少なかったように思う。食べ物から身の回りの物すべてを、いかに買い物で手に入れていたかがよくわかる。
とは言え、私は子どもたちの将来のために、食べ物を始め、身の回りのものについてその原料や作り方、材料になる生き物の成長の様子を知って欲しいと思う。しかし、一緒に野菜を育てようと思っても、土を触らせれば汚いと言い、虫がいれば怖がる子どもたちにどのように興味を持ってもらえばいいのだろうと悩んでしまう。
農文協の絵本に「そだててあそぼう」という絵本シリーズがある。ヒマワリやキクのような花から、ヤギやウサギなどの動物、キュウリやナスなどの野菜などの生き物の生態や育て方、歴史などをそれぞれ一冊ずつの絵本にしたものだ。全部で一〇五巻ある。
もちろん『ラッカセイの絵本』(すずきかずお編/ひらのえりこ絵/農文協)もあって、ミスターピーとミスターナッツのかわいい二人?の案内で、落花生の花が咲いた後に土の中で実る様子や数々の品種や歴史、詳しい育て方や色々な調理方法まで紹介されている。この絵本なら子どもたちも興味を持って読んでくれるのでうれしい。
私は、この「そだててあそぼう」の絵本シリーズが好きで、ハロウィンに近くなれば図書館から『カボチャの絵本』を借りてくるし、ヤギのことを知りたい時は『ヤギの絵本』を借りてくる。子どもだけでなく、大人だって専門外のことを学ぶには、絵本だとわかりやすくて便利だ。
*
さて、ピーナッツがどのように実を付けるのかについて無関心な子どもたちだったが、味わうことに関しては別だ。子どもたちとピーナッツバターを手作りしてピーナッツバター&ジェリーサンドを作ったことがある。ピーナッツからピーナッツバターができる過程に興味津々、それを使ってできたピーナッツバター&ジェリーサンドを食べた時の喜び方は、土の中から落花生を掘り出した時とは雲泥の差だった。
大人の会話でも、子どもの頃食べた給食の味や、畑で収穫したとれたて野菜を味わった時のことなど、食べ物の思い出話は多い。
*
そんな味覚の記憶を思い出すからだろうか。おなじみの絵本『ぐりとぐら』(中川李枝子作/山脇百合子絵/福音館書店)も、「二匹の野ネズミのおはなし」と言うよりも「大きなフライパンでカステラを焼くおはなし」と言った方が「あっ!あの本ね」と思い出してもらえる。
福音館書店の五十周年記念出版された本に、『ぼくらのなまえはぐりとぐら』(福音館書店母の友編集部/福音館書店)がある。ぐりとぐらの生みの親の二人の対談や絵本『ぐりとぐら』ができたころの話、各界の著名人のぐりとぐらの思い出や作品評などが収められている。絵本のカステラの作り方や、ぐりとぐらのお人形の作り方も書いてある。
ぐりとぐらの名前はフランスの絵本の中に由来していることや、ぐりとぐらのような黄色の野ネズミが本当にいて、それをモデルにしたことなど、この本を読むとちょっと物知りになれたような気がしてうれしい。
中でも一番興味深いのは、「『ぐりとぐら』を読む」と題した長谷川摂子の評で、子どもたち同士が同じ空間にいても並行遊びしかできなかった幼い子どもが、三歳前後で自分と似た子を見つけ出して友達を作る、その頃の意識を「ぐりとぐら」というそっくりな野ネズミで描きだしているからこそたくさんの人々の支持を得ているのではないかと述べていることだ。
大人に守られているときとは違う、子ども同士のつながりで社会を作りだす幼い子どもたち。彼らそっくりのぐりとぐらが、食べるという生命の喜びを得て幸せでいる様子を読むことは、この世は楽しくすべてうまくいくんだという人生への信頼を子どもへ伝えてくれているのだと。
*
この五十周年記念出版物の『ぼくらのなまえはぐりとぐら』には、物語のはじめに「ぼくらのなまえは ぐりとぐら…」でぐりとぐらが歌う歌詞に各家庭で付けられたメロディーの楽譜集も載っている。実に様々なメロディーがあって、それも一つとして同じものがないのが驚きだ。もちろん、私が子どもたちに読んであげていた時のメロディーと同じ楽譜もない。
歌のバラエティが豊富だということは、読んであげる大人の数、読む子どもの数だけこの短い物語によって作られたイメージがあるということになる。同じレシピでも作り手によって味が違うように、みんなそれぞれが家庭の味ならず家庭のイメージでこの物語を楽しんでいたのだ。
今は、一歳の子どもでもYouTubeを楽しむ時代だけれど、時にはタブレットやスマホを子どもから取り上げて、絵本を読んであげて欲しいと思う。手作りの母の手料理の味も、慣れていなければ買ったものの方がおいしいといわれるようになってしまうのだから。
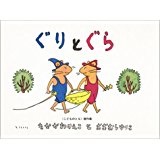
『ぐりとぐら』福音館書