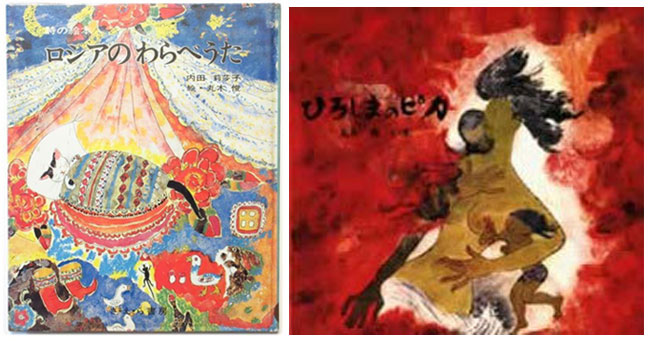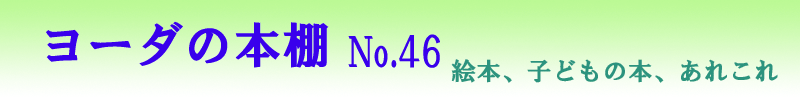
2017年9月13日 発行
■平和の「音楽」を
子どもが、感じるものを考える
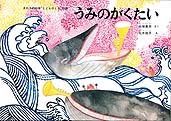
『うみのがくたい』
大塚雄三さく/丸木俊え/福音館書店
先日、生まれて初めて二胡を弾いた。二胡はバイオリンや三味線に似た形の中国の伝統楽器で、張られた二本の弦を竹と馬の尾の毛でできた弓でこすって音を出す楽器だ。
先生の教えに従って、楽器をケースから出して膝の上に構え、持ちなれない弓を持って、弦をこすってみると、ガサガサ、ギギギー…。ラジオやテレビなどで聞く、哀愁を帯びた美しい音色を想像していたのに、そんな美しい音色なんていつまでたっても出てこない。
ぎこちない動きで変な音を出しているおばちゃんを、はたから見ていたら、さぞ可笑しいだろうなと恥ずかしく思ったが、少しでもいい音を出そうと無心になっている時間はなかなか楽しい。音階ができるようになって、曲が弾けるようになれば、二胡を演奏する時間は、もっと素晴らしくステキな時間になるんだろうなと思った。
*
さて、九月の大人のための子どもの本を読む会のテーマが「音楽」というので、何か良い絵本はないかなと思っていたら、ラボ・パーティのカレンダーの絵に目が留まった。『うみのがくたい』(大塚雄三さく/丸木俊え/福音館書店)を聞いた子どもが、この物語の中の、楽器を演奏する三頭のクジラたちを描いた絵だ。
広い海の上を進む一隻の船。この船で働いている人たちは音楽好きで、夕方になると甲板に並んで合奏するのだが、音楽が始まるとクジラやイルカ、魚たちが集まってくるようになっていた。ある日、嵐がやってきて、船が沈むかと思いきや、クジラたちが船を支え沈没を免れる。
助かった船乗りたちは、お礼に、自分たちも演奏してみたいというクジラや魚たちに楽器を渡し、それからその辺りの海を通ると不思議な音楽が響いてくるようになったという物語だ。海の生き物たちが悪戦苦闘しながら楽器を演奏する様子を想像するととても楽しいし、美しいハーモニーが流れる夕焼けの海を想像すると、心が洗われるような気がする。
子どもたちがラボ・パーティで活動するときは、絵本だけでなく、CD音源も聞く。『うみのがくたい』の物語は、間宮芳生による音楽と江守徹による朗読の声もとても合っていて、古い絵本だが未だに子どもたちに人気がある。
なので、私たちラボ・テューター(ラボ・パーティの先生)たちの間でも、よく話にあがる。昨年も舞台で発表した子どもたちがいて、その活動の報告をしていた時のこと、経験の長いテューターが、「この話、鎮魂の物語だねって子どもが言ったって話、知ってる?」と言ったのだ。
音楽を演奏するのは、海で死んだ人のためだと言った子どもがいたのだそうだ。絵本にはそんなことは一言も書いていないのに、なるほどと思う一言だと経験の長いテューターの間では語り継がれている話題なのだそうだ。
*
ところで、以前、子どもの本を読む会でロシアの絵本を取り上げたことがあったのだが、その時、『ロシアのわらべうた』(内田莉莎子/丸木俊絵/架空社)が話題になった。この本は、明るく幸せで楽しげな絵が描かれた古い本で、大切に保管されていたものを、まちの本棚に寄付して頂いたものだ。その本を見た瞬間、みんなから「丸木俊さんって、原爆の図の?」と驚きの声が上がった。
『原爆の図』は丸木伊里、丸木俊夫妻が、原爆投下直後の広島に入り、その時に見た様子を元に、原爆の悲惨さを描いた一連の作品だ。一度見たら、その酷さを忘れることができないすごい絵だ。絵本でも戦争の惨状を伝える本をたくさん残していて、『ひろしまのピカ』(丸木俊作/小峰書店)を読んだことがある人も多いと思う。
近頃、北朝鮮がミサイルや核爆弾の実験を繰り返していて、世の中が騒がしい。そういう世の中の様子を、子どもたちは敏感に感じる。ミサイル発射を告げるJアラートの警報が鳴って驚いたその何日か後、ラボ・パーティで『すてきなワフ家』(C.W.ニコル作/ラボ教育センター)という犬の家族の物語に取り組んだ時の事だ。
配役を決めて、物語に従って劇ごっこを始めた私たち。いつものように役になりきっていた子どもたちだったのに、この物語には犬たちが地下室を作るシーンがあって、その場面になると、子どもたちの様子がいつもと違う。「ミサイルが来るから地下室掘らなくちゃ!爆弾が来たら地下に逃げるんだよ!」と大騒ぎになって、この後の物語を続けることができなくなってしまった。
思った以上に、あの警報音は子どもたちに強い影響を与えていたのだ。子どもたちの大騒ぎを収拾するために、私は思わず、「自然災害は備えるしかないけど、ミサイルは人間がスイッチを押さなきゃ来ないんだよ!爆弾のボタンを押さなきゃ大丈夫なんだから?」と大声で叫んでしまった。
以前なら、この地下室を作るシーンでは、子どもたちは必ず「なんで地下室を作るの?」と質問してくるので、「アメリカの家には大きな地下室があるんだよ。映画の『ホーム・アローン』でも地下室に洗濯機があるし、ほら、『オズの魔法使い』でも竜巻が来た時、地下室に逃げるじゃない…」なんていう楽しい会話をしたのだ。警報一つで、子どもたちの心があっという間に変わってしまって、何だか悲しい。どうして、ミサイルや爆弾が世界から無くならないのだろう。
教室で子どもたちが大騒ぎをした後、私は一人で『ひろしまのピカ』を読んだ。『原爆の図』ほど、悲惨な状況を描いた絵ではないが、原爆投下後の様子を描いた絵は見るのも辛い。けれど、これが核爆弾が引き起こす現実なのだ。読み進めて、物語の最後の文章を読んで驚いた。「ピカは、ひとがおとさにゃ、おちてこん」(『ひろしまのピカ』本文より)と。私が叫んだことと同じだ!
最近気が付いたのだが、『うみのがくたい』の絵も丸木俊だった。『原爆の図』や『ひろしまのピカ』とは全く違う色鮮やかで楽しげな絵で、私は気が付かなかったが、子どもたちは、『うみのがくたい』の中に、鎮魂の思いで絵を描き続けた丸木俊の平和への思いをちゃんと感じていたのではないだろうか。
私にはミサイルのスイッチを押すのを阻止する術はない。けれど、子どもたちに絵本を読んであげたり、いっしょに物語を楽しんであげたりすることはできる。平和の願いが込められた作品を子どもたちに伝えるのは、小さな動きかもしれない。だけど、小さな波紋でも起こせば、いつか核のボタンを押そうとする人の手の動きを止めることができるくらい大きくなるかもしれない。そう思ったら、少し元気が出てきた。