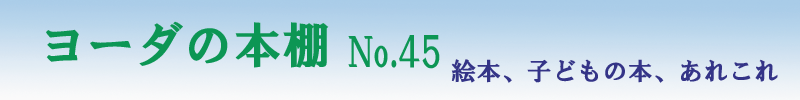
2017年7月12日 発行
■絵本の中の夜
ヒトが成長し、大人に向かう時間
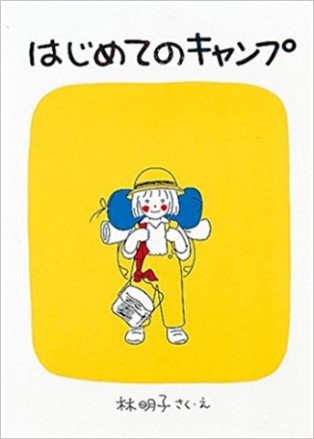
『はじめてのキャンプ』/林 明子 さく・え/福音館書店
病院の待合室で読み始めたら、そこにいた子どもたち全員が釘付けに。
厚みのある本だが、幼児から小学生まで楽しめる。
林明子の色を抑えた絵も線が際立っていい。
夏休みは、子どもたちが、祖父母の家にお泊りに行ったり、いろいろな団体が企画するキャンプに行ったりと、両親の元を離れて夜をすごすことの多い季節だ。
私も夏は、ほぼ毎年のようにラボ・パーティのサマーキャンプに参加する。『はじめてのキャンプ』(林明子さく・え/福音館書店)みたいに、テントを張って、自炊するわけではないけれど、小さな子もいれば、大きな子もいる三泊四日のキャンプ。
毎日夕方になると決まって泣き出す子や、みんなといっしょにお風呂に入れなくてオロオロする子、話しかけられなくてモジモジする子がいるかと思えば、甲斐甲斐しく小さな子を世話するお姉さんもいたり…。
そんな子どもたちも、最終日の夜は、怪談話に恋の話、学校や家族の悩みを話すなどで仲間と大騒ぎ。行きのバスでは不安でいっぱいの顔をしていたどの子も、帰りのバスでは疲れて眠りこけながらも、自信のあふれた顔になっていて、親元を離れて夜をすごしてくることは、本当にすごい冒険なのだと思う。
『はじめてのキャンプ』じゃないが、キャンプやお泊り会などでは、どういう訳か、小学校高学年ぐらいになると、夜寝る前に必ず「怖~い話して!」と言い始める。私は怖い話をするのは嫌いなので、仕方なくいつも昔話を語るのだが、普段は騒いで人の話を聞かない子も、この時だけは神妙な顔で聞いてくれる。
こんな時は、本来は、夜にこそ昔話を聞くものなのだなと改めて思う。
二十年ぐらい前、絵本などを読まないでお話だけを子どもたちの前で語る〝素話〟というものを始め、お話をいくつか覚えたのだが、その中にグリム童話の『おどっておどってぼろぼろになったくつ』という昔話があった。
たくさんあるグリム童話から、何気なく選んだ話だったが、語るたびに表面に語られている言葉の意味以外にも深い意味を感じる話だった。
昔あるところに王様がいた。王様には十二人のお姫様がいたのだが、朝起きると必ず、お姫様たちの靴は、どれも散々踊った後のようにボロボロになっていた。王様はお姫様たちに問いただすが、お姫様たちも何も言わないし、毎夜どこに行っているのか、誰にもわからない。
そこで、王様は、お姫様たちの隣の部屋に泊まって、何をしてきたのか突き止めた者は、お姫様たちの一人を妃にし、王様の亡き後はその位を譲るが、三日たってもわからなければ首を跳ねるという御触れを出す。たくさんの王子がこの難題に挑戦するが、みんな首を跳ねられてしまう。
ところが、たまたまこの国を、怪我をした貧しい兵士が通りかかる。兵士は、道端で出会った不思議なおばあさんに助けられ、この難題に挑みめでたく謎を突き止める。
結局、お姫様たちの秘密は、毎夜、地下の不思議なお城で、十二人の王子たちと夜遊びをしていたんだとひと言でいってしまうと身も蓋もないのだが、地下の国に行く準備をするお姫様たちが、タンスからドレスを取り出し、嬉しそうに鏡の前で飛んだり跳ねたりする様子や、地下の国の湖の向こうに光を放つお城、船でお姫様たちを出迎える王子、お城での様子。
それらの情景を語るたびに、毎夜、どんなにかきらびやかだったのだろうと、うっとりとしたものだ。
このお話のみならず白雪姫にだって、昔話には、必ず、その裏に隠された教訓があるという説もある。昔のみならず今の時代も、夜の繁華街は大人のお楽しみの場所で、きらびやかな世界につられて、子どもが間違って一歩踏み込めば、誘惑に負けてしまって、とんでもないことになってしまう。
現在は、二十四時間コンビニエンスストアに明かりが灯り、子どもだって夜の街を歩いていることもあるけど、夜の世界には恐ろしい魔物がいることを忘れてはいけないと思う。
ところで、子どものための絵本ではないけれど、『ゴブリンマーケット』(クリスティナ・ロセッティ文/ローレンス・ハウスマン絵/井村君江監修/濱田さち訳/レベル)がある。作者のクリスティナ・ロセッティは、十九世紀のイギリスの女流詩人。
『歌う歌』(Sing Song)という童謡集が代表作で、子どものための色彩豊かな詩を書いている。西条八十が訳した「風」は、スタジオジブリの映画『風立ちぬ』でも主人公の二郎が口ずさんでいた。
『ゴブリンマーケット』は童謡のような形だが、内容は官能的で子ども向けではないという。悪い妖精・ゴブリンたちは、リジーとローラの二人の乙女に誘惑のくだものを食べさせようとする。誘惑に負けてしまった妹のローラ。ゴブリンのくだものの味に恋い焦がれ、ローラは日に日に弱っていく。
リジーは、妹を助けようと決心し、ゴブリンのもとに向かう…。
クリスティナ・ロセッティは、一八六〇年に売春婦更生院で働いた経験があり、それがこの詩に影響しているのではないかという。『ゴブリンマーケット』は大人のための詩だというが、私には、どこかグリム童話と似通っているように思えてならない。
先日、石巻絵本とおはなしの会主催のおはなしの勉強会で、仙台の川端英子さんの素話を聞いた。川端さんは、仙台弁でグリム童話の笑い話を語る他、最後にグリム童話の『ねずの木』を語って下さった。この話は、継母が前妻の子を殺し、死体をスープにして父親に食べさせてしまうといった怖い話だ。
こんな怖い話、嫌だなと思いつつも、聞き終わってスッキリ楽しかったという気分になった。昔話や詩や物語は、その物語が持つ表面的な意味だけでなく、例えば無意識というような人間のもっと深いところに話しかけてくれるものだという。
だから、大人も子どもも、恐ろしい怖い話もエロティックで不思議な話も、聞いた後はそんなことは忘れて、スッキリするのではないだろうか。そういえば、私が幼いころは、親戚一同が集まった席では、嘘か本当か、誰かが首つりをした話などをキャーキャー言いながら、大人も子ども関係なく聞いていた気がする。
今、ラボ・パーティの私のグループの子どもたちは、クリスティナ・ロセッティの『ピンクは何?』(What is pink?)という詩を発表会のために暗唱している。たぶん、言葉の意味なんて分からないと思うが、私は「覚えるの嫌だ!面倒くさい!」という子どもたちを、一生懸命説き伏せている。きっと大人になっても心の深くに、その鮮やかな詩の世界が残るのではないかという思いで…。
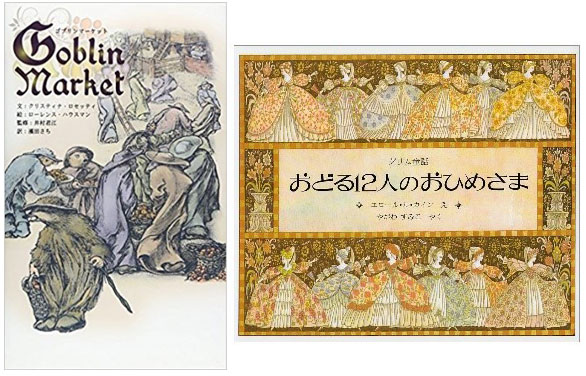 ㊧『ゴブリンマーケット』レベル刊ローレンス・ハウスマンの挿絵だけでなく、同じく十九世紀に活躍したアーサー・ラッカムやマーガレット・タラントの挿絵も添えられている。 絵の違いを比べるのも楽しい。
㊨ 『おどる12人のおひめさま』グリム童話/
|