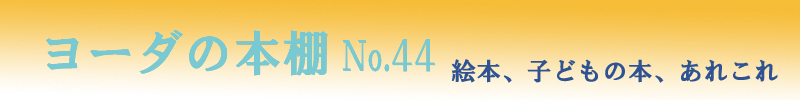
2017年6月14日 発行
■絵本の中のお母さん
絵本に教わった子どもとの接し方
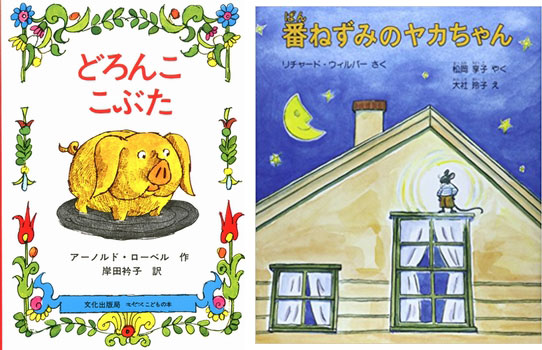
㊧『どろんここぶた』アーノルド・ローベル作/岸田衿子訳/文化出版局
㊨『番ねずみのヤカちゃん』リチャード・ウェルバーさく/松岡享子やく/大社玲子え/福音館書店
土日でラボ・パーティの私のグループでお泊り会をした。久しぶりのお泊り会の開催で、参加した子どもたちはみんな私の家での一晩は初めての体験。知らない家のはずなのに、お風呂の時間になると、「先生来なくてもいいよ」とさっさとお風呂に向かう女の子たち。心配して私が「使い方わかる?」と聞くと、「お祖母ちゃん家と同じだから大丈夫」との声。
お泊りした子どもたちのお母さんたちも、私よりも娘の年齢に近いし、娘との方が話も合うようで楽しそうに話している。まだまだ若いつもりだったけど、私はおばあちゃん世代なのね、とちょっと寂しくなった。
最近は、お祖父さん、お祖母さんに昔と今の育児の違いを教える教室があるくらいだから、育児方法も世代によってずいぶん違いがあるのだろうと思う。娘たちはわからないことがあると、すぐにスマホで検索するが、今のお母さんたちも子育てのヒントはスマホから得るのだろうか。おばあちゃん世代の私は、絵本に親としての態度を教わることが多かったように思う。
子どもが小さかった時に何度も読まされた本に『どろんここぶた』(アーノルド・ローベル作/岸田衿子訳/文化出版局)がある。お百姓夫婦のもとで暮らしている子豚が何よりも好きなことは、やわらかーい泥の中に座ったまま沈んでいくこと。子豚がかわいくて仕方ないおじさんとおばさん。
ある日、おばさんは大掃除を始め、豚小屋もきれいに掃除し、ついでに子豚もお風呂へ。子豚はきれいになって、リボンまで結んでかわいくなったのに不満顔。家がピカピカすぎてつまらないのだ。子豚は、とうとう家出を決心。どろんこを求めて旅をするが、子豚は気に入ったどろんこに出会えずに、最後は大きな町までやってきてハプニングに巻き込まれてしまう。
一方、お百姓夫婦も子豚を探しまわり、町にやってきた。子豚は無事におじさん、おばさんに出会い、どろんこのある我が家へ帰る。ストーリーも楽しいが、「やわらかーいどろんこ」の中に「ずずずーっ」と沈んでいくという言葉の繰り返しが楽しい。黄、青、黒色の地味な色彩の絵本だが、幸せそうな子豚の表情に心がほのぼのとする。
『どろんここぶた』は楽しくて、私の大好きな絵本なのだが、ある日、読みながらふと気が付いた。「あなたの家は大丈夫?」と言われているような気がしたのだ。もちろん、掃除のしすぎで家がきれいになりすぎているわけではない。「子どもを無理に着飾らせようとしていない?」「子どもの好きな物を取り上げてしまっていない?」と言っているように感じたのだ。
こんな風に、読むたびに諭されているような気がした絵本に、『番ねずみのヤカちゃん』(リチャード・ウェルバーさく/松岡享子やく/大社玲子え/福音館書店)がある。この絵本は、私の読み聞かせの定番で、生き生きとした表情の絵が良いだけでなく、途中文字が大きくなっているので、それに合わせて声の大きさを変えて読むと本当に面白く、どんな子も最後まで物語を楽しんでくれる一冊だ。
お母さんねずみと四匹の子ねずみは、人間のドドさんの家の壁の隙間に住んでいる。四匹の子ねずみのうち三匹は静かだが、一匹は声の大きなヤカちゃん。お母さんねずみは、子ねずみたちが自立して暮らしていけるように色々なことを教える。もちろん、人間に見つからないように静かにすることも。けれど、どうしても声を小さくすることのできないヤカちゃん。
ヤカちゃんの大声は困った欠点のはずなのに、仲間に危険を教え、ドドさんにネズミ捕りは無駄だと思わせ、怖い猫もビビり、最後にはヤカちゃんたち一家が一生安心して暮らせるような結果を招いてくれる。
子どもに何度教えても理解してくれないことがある。「どうしてこんなことも分からないの!」「どうしてできないの!」と思うけれども、『番ねずみのヤカちゃん』を読んでいると、あんまり教えすぎるのも良くないのではないかと思えるのだ。今の小学生の六十五パーセントが大学卒業時に今存在していない職に就くという。今の大人の価値観で矯正したって、将来、必ず役に立つとは限らない。何でもガミガミ教える必要はあるまい。
とは言え、ヤカちゃんのお母さんは、大切なことはしっかりと歌にしてヤカちゃんたちに教えている。ヤカちゃんが猫に近づいて挨拶をしようと思った時、何かがキュッキュッとヤカちゃんを引き留め、お母さんの歌を思い出し災難から逃れることができる。ヤカちゃんの大声にガミガミ言わず、子どもに覚えていて欲しい事は、しっかり教えているヤカちゃんのお母さんはすごいと思う。
災難から逃れると言えば、『チム・ラビットのぼうけん』(A・アトリー作/石井桃子訳/中川宗弥画/童心社)では、子うさぎのチムは、いかにも楽しそうなステキな生き物に話しかけようとするが、危ういところで話しかけずに逃げ帰る。こちらは、チムに危険を教えてくれたのは、風や雷や雹たち。家に帰ったチムは、お母さんからその生き物は犬だと教わる。
チムは最初、風や雷、雹に会って驚くけれど、自然現象は怖いものではないとお母さんが教えてくれていた。チムは小さな冒険を繰り返して、学んでいた。だからこそ、自然現象に関心を示し、大きな危険を回避できたのだ。
このおはなしでは、チムが小さな冒険から帰ってくると、お母さんは必ず美味しいパンやケーキを焼いて待っている。お母さんが待っているからこそチムは安心して冒険に出かけることができた。私もこんな風にいい匂いのする家で外から帰ってくる子どもたちを待ちたいと思ったのを思い出す。
思えば、『せんたくかあちゃん』さとうわきこ作・絵/福音館書店)のかあちゃんみたいに、私もたくましく明るい母ちゃんになりたいと思ったけれども、実現しないうちに子育ても終わってしまった。
むしろ、私は『ちゃんと たべなさい』ケス・グレイ文/ニック・シャラット絵/よしがみ きょうた訳/小峰書店)のお母さんに近かったかも。主人公のデイジーはお豆が大嫌い。お母さんは、デイジーにお豆を食べさせようとお豆を食べたら、夜更かししてもいいし、お風呂に入らなくてもいいし、自転車やゾウやペンギンも買ってあげるからと次々に条件を示す。
その条件が普通じゃない。読みながら、もし、デイジーがお豆を食べたらどうするんだろうと思ってしまう。結局、デイジーはお豆を食べず、お母さんだって好き嫌いがあるのだから、嫌いな芽キャベツを食べたら私も食べるとデイジーの側が条件を示す。
ついつい大人は子どもを思い通りにしたいと思うが、子どもは大人のことなんかお見通し。何か教え込もうと思っても無駄なこと。親子そろって、笑って、美味しいものを食べるのが一番大切なことなのかもしれない。
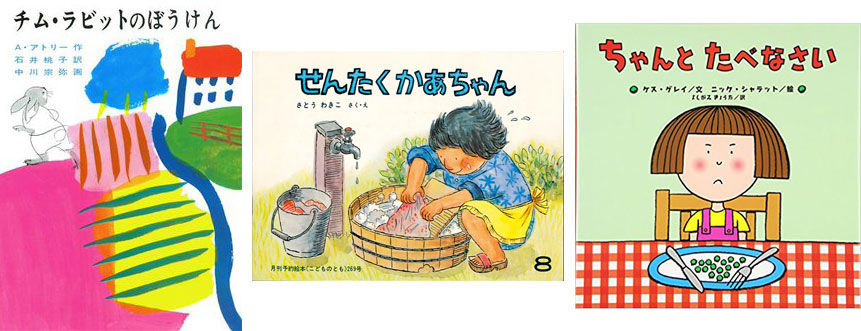 ㊧『チム・ラビットのぼうけん』A・アトリー作/石井桃子訳/中川宗弥画/童心社 |