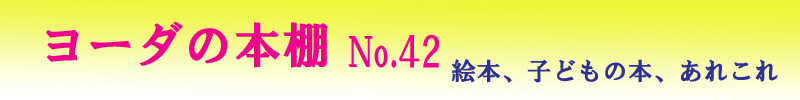
2017年4月11日 発行
■ともだち作りは大変だ!
子どもの心を育てることの難しさ

『百まいのドレス』』
エレナー・エスティス作
ルイス・スロボドキン絵
石井桃子訳
岩波書店 2006年
新学期、子どもたちは、新しいクラスメイトと新しい生活を始める季節だ。特に新一年生はほとんど知らない子どもたち同士が集まって新生活を送ることになるのだから、新学期の子どもたちの混乱と学級を運営する先生のストレスは大変なものなのだろうと思う。
私の教室でも、つい最近、ずっと二人で活動していた小学一年生二人のクラスへ、一つ年下の新人が一人加わった。すると、いつも優等生の女の子が、活動を始めて三十分ぐらいすると、毎週のように部屋の隅で泣き出して、ふて腐れてしまうようになった。一度すね始めたら、私や他の子どもたちが何を言っても、おやつで気をそらしても泣き止まない。どうやら、新人くんと一緒に仲良く活動をしたいようなのだが、自由人の新人くんが自分のやりたいように振る舞うのが気に入らないらしい。かといって、彼を制することもできず、そこで泣いてみたけれど、ますます自分の感情がコントロールできなくなって、自分でもどうしたらいいのか収拾がつかなくなるようなのだ。
人間は三人集まると社会を形成するそうだ。だから、三人兄弟ならば社会性が育つが、二人兄弟ではどこかで社会性を学ばなければいけないらしい。教室の中でも、三人になったとたんに小さな社会が形成されたわけだ。きっと、さっきの女の子は、これから試行錯誤する中で自分の感情をコントロールするすべを身に付け、新人くんを導く力をつけていくんだと思うが、見守っている私の方は、ラボに行くたびにやりたいことができなくてイライラ。「縦長の活動で社会性が育つ」というのが、ラボ・パーティの売りなんだから、喜ぶべきことなのだが、この状況に対応するには大人の側に相当な忍耐力が必要だということを実感した。
石巻図書館の子どもの本を読む会で、『百まいのドレス』(エレナー・エスティス作・ルイス・スロボドキン絵・石井桃子訳・岩波書店)を読んだ。この本は、戦後間もない一九五四年に『百まいのきもの』という題名で「岩波子どもの本」シリーズの一冊として出版されていたものだ。今回、五十年ぶりにもう一度石井桃子氏により訳され、絵も現代の印刷技術で美しく再現されたのだそうだ。
主人公のマデラインと学校で一番の人気者のペギーは、ある日、影の薄いクラスメイトのワンダが学校に来なくなったことに気が付く。ワンダは、町はずれの小さな貧しい家に住み、いつも同じ皺だらけの色がはげたうす青色のワンピースを着ているが、クラスメイトには「うちに、ドレス百まい、持ってるの」と答える。ペギーとマデラインをはじめ、クラスメイトみんなは、そんなワンダを面白がって繰り返しからかっていた。けれども、マデラインは、ペギーといっしょにワンダをからかいながらも、心には何か引っかかるものがあった。マデラインは、心の引っかかりを解消するために何をすべきか、思い悩む日々が続く。この本には憎むべき敵もヒーローもなく、心躍る大冒険も語られているわけでもない。けれど、微妙なマデラインの心の動きやワンダやその家族に対する大人たちの偏見や差別、個々の子どもたちのワンダに対する気持ちの違いなどが細やかに綴られていて、読み進めるうちにどんどん物語に引き込まれてしまった。
世の中では「いじめはダメ」とか「いじめを無くそう」という言葉が繰り返し叫ばれ、「いじめ」がなくならないのは道徳教育が教育カリキュラムとして授業に組み込まれていないからだという大人もいるが、そう言っている本人が、「いじめ」とはどのようなものなのか本当に分かっているのだろうかと不思議に思うことがある。人はそれぞれ違う考えを持っていれば、必ず対立は生まれる。相手が何を考え、何を感じているのかを想像し、仲間たちとどう関わるのがいいのか、時には小さないじめや喧嘩を繰り返しながら試行錯誤して身に付ける時期が子ども時代だと思う。スタジオジブリの映画『天空の城ラピュタ』のシータのお祖母さんも「いい言葉に力を与えるには、悪い言葉も知らなきゃならない」と言ってシータに滅びの言葉を教えていた。子ども時代に、悪いことも良いことも体験する機会を作ってあげることこそ大事ではないのか。子どもに「いじめを無くそう運動」をさせるのが最良の方法ではないはずだ。
この『にほんご』、読んでいて面白いなあと思ったのは、普通の教科書ならば「じを かこう」とか「おおきな こえで よみましょう」と単元の内容を書くところを、「おぼえちゃおう」とか「おもいえがく」と書いていることだ。「うそ」なんて単元もあって面白い。「おぼえちゃおう」には、谷川俊太郎の『ことばあそびうた』の中の「かっぱかっぱらった…」という詩もある。「ごめんね・ありがとう」の単元には、『いちねんせい』(谷川俊太郎・詩/和田誠・絵/小学館)という絵本の中の「わるくち」という詩の一部が書かれている。私は、この詩をペープサートを使って子どもたちに紹介することがあるが、すると子どもたちはいつも笑いながらも不思議な顔をする。悪口をこんなに公然と言っていいのかというような顔で。
話は変わって、英語圏では、児童文学と大人が読む文学一般の図書の間にヤングアダルト文学(略してYA)という分野を設けている。古いものでは、『トム・ソーヤの冒険』や『不思議の国のアリス』、『宝島』などがそれにあたるそうだ。日本では、ジョブナイルと言ったり、ライトノベルも含んだりするらしい。私は、時々、一般文学を読むほど元気はないし、かといって絵本じゃ物足りないときにこの分野の本を読む。そんなYA文学の一冊に、『鬼にて候』(横山充男作・橋賢亀絵・岩崎書店)がある。主人公の保のクラスに若い男性教師がやってくることで始まるこの物語、この本の冒頭でこの教師の発案で毎日何か良いことを見つけて記入する「いいこと日記」が奨励され、いつしか数名の子どもたちが自発的に「いいこと委員」を名乗り活動を始める。すると、かえってクラスの雰囲気は悪化し、クラスでいじめを思わせる事件が次々と起こり始める。結局、これらの事件は悪霊の仕業で、鬼道師の家系に生まれた気弱な主人公の保は、無事鬼道師デビューを果たし、事件は一件落着というストーリーなのだが、この「いいこと委員」が現実の学校にもありそうで、この本を読んで、なんだか不気味な気分になったのを覚えている。
昨年末、絵本専門士の講座のために『メディアにむしばまれる子どもたち―小児科医からのメッセージ』(田澤雄作著・教文館)という本を読んだ。この本は、仙台市で子どもたちを診療し治療をしている小児科医が、原因不明の頭痛や腹痛を訴え診療にやってくる子どもたちの多くが、電子メディア漬けや早期教育、スポーツで心も体もへとへとになっていることを訴えたものだ。問題行動を起こして病院に来た小学六年生や四年生の子どもたちは、必ず「学校で暴れまくる原因がわからない」ために、「悲しい、さびしい、つらい」思いをしていたという。まるで、小学一年生の女の子の行動と心にそっくりだ。
テレビ、ビデオ、ゲームの世界にいる時間が一日平均四時間の場合、睡眠時間を差し引くと、現実的な体験が四分の一減る計算になり、結果、例えば十二歳の子どもは、四分の一に当たる三年を引くと九歳なので、体は小学校高学年でも、心は小学校低学年なみにしか発達していないことになると書いている。こうやって数字で示されるとなるほどと思う。
ちなみに、田澤先生は、子どもには「原因はテレビゲームだよ。だまされたと思ってやめてみたら」と助言するらしい。すると、どの子もゲームをやめて二週間ほどすると落ち着くそうだ。
いじめる方もいじめられる方も幼いがためにおこるいじめもあり、時には幼い子どもたちに取り囲まれてまともな子どもがいじめられるケースもあるそうだ。どんな風に育っても、今の子どもたちは大変だ。せめて、大人がもう少し物事の本質を理解していれば子どもも生きやすい。子どもの本なんてと言わずに、大人が『百まいのドレス』を読んでみるのもいいかと思うのだが。
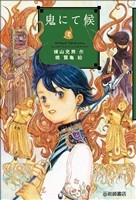 『鬼にて候』 |
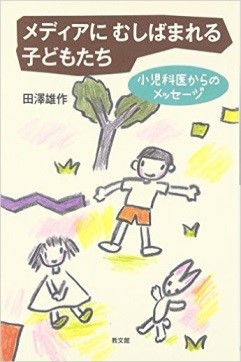 『メディアにむしばまれる子どもたち―小児科医からのメッセージ』 |