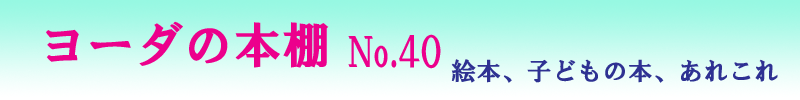
2017年2月7日 発行
最近、ニキビができて困っている。ネットで調べたら、大人ニキビと言うらしく、10代のニキビと違ってあごの辺りに多くできるらしい。確かに、私のニキビも右あごにある。保湿に心がけて、出来たニキビは触らないようにするのがいいらしい。でも気になって触っちゃうんだよな〜。それに化粧するのも面倒。なので、ノーメイクでマスクをして外出することにした。知り合いに会わないように用を済ませ、最後に図書館によって帰ろうと思ったら、貸出カウンターで「先日、借りた本はいかがでしたか?」と司書さんに声をかけられた。さすが図書館員!私は司書さんの顔を忘れていたが、彼女は私の顔を覚えていたようだ。 以前、私よりひと世代前のご婦人方とお茶をした時に、ステキなご婦人が「朝起きたらすぐに化粧をして身だしなみを整え、それから台所に立つのよ。だって、いつ誰に合うかわからないじゃない」と話していたのを私には無理だと思いながら聞いていたことがある。あ〜ぁ、年を重ねれば重ねるほど、記憶が弱くなる分、そういう心がけは大事になるんだろうなぁ。
■小学校の教科書

『にほんご』
安野光雅・大岡信・谷川俊太郎・松居 直/編
福音館書店
大人になると、書かれた文字を声に出して読むことはほとんどない。小説はもちろん、新聞もチラシもパソコンの画面だって、時々声に出して読んでいる人を見かけると不思議に思ってふり返ってしまう。子どもにしたって、声に出して読んでいいのは国語の音読の時間ぐらいで、小学1年生でさえテストの時に声に出して読んでいたら怒られてしまう。そうやって文字は目で読むものと教え込まれた子どもたちが中学生になって、英語は声に出して読みながら覚えるものだと言われてもできないのは無理もないことだなと思う。
それが大人になって子どもが生まれたりして周りに幼い子がいるようになると、声に出して絵本を読むようになる。我が家も子どもが生まれて寝る前に絵本を読む習慣ができたが、そうなると、主人も私も最初はたどたどしかったのに、知らないうちに声に出して文字を読むのが上手くなっていて驚いたことがある。20年前に書いた自分の文章にも「新聞の記事を読み上げていると、自分でも不思議なくらいスラスラと読めた」なんて書いてある。そもそも絵本は声に出して読んであげることを前提に文章を書いている。どんなことでも良質のものに多く触れれば力が付くものだ。絵本をたくさん読んで良質の文章にたくさん触れたのだから、自然と声に出して上手く読む力が付くのは当然だ。
そんな絵本の文章の中でも、わらべうたや詩を絵本にしたものは声に出すこと自体が楽しい。もう20年ぐらい前の話だが、小学校に読み聞かせ行った時、いっしょに行ったメンバーが、谷川俊太郎の「うとてとこ」の詩に身振りをつけて紹介していて、なんて面白いんだろうと思ったことがある。この詩は『ことばあそびうた』(谷川俊太郎詩 /瀬川康男絵/ 福音館書店)の中の15編の詩の中の一つだ。この絵本には、和風なユーモラスな絵と手書きの文字が書かれていて、文字自体も絵のようだ。どの文字を目で追ってもしばらくは意味が分からないが、声に出して見るとリズミカルでとても楽しい。
私は大人になってから谷川俊太郎は『二十億光年の孤独』などの詩集を刊行している有名な詩人なのだと知った次第だが、作家の高橋源一郎が寄稿したサイトによると※、今の大学生たちは現代詩人の名を一人として知らないのに、谷川俊太郎だけは全員知っていたらしい。詩はもちろん、翻訳した作品も教科書にも取り上げられているし、たぶん、大学生だけでなく今の子どもたちにとっても一番なじみのある作家だと思う。
そんな谷川俊太郎が編集委員の一人になっている『にほんご』(安野光雅/大岡信/谷川俊太郎/松居 直/福音館書店)という本がある。この本は、文部科学省(発刊当時は文部省)学習指導要領に従って作られているわけではないが、小学校1年生の国語教科書を想定して作られたものだ。「おはよう」のあいさつに始まって、外国語や方言の例も載せ、今使っている言葉は地球上にあるたくさんの言葉の一つであること、さらにいろいろな文体があること、文字の歴史、そして何よりもこの本を読むと言葉は自分と他人との間の関係をつくるものの一つであることがわかる。
今の小学校の教科書をみると、自分が子どもの頃の教科書と随分違っている。何よりも違うのはサイズの違いだが、文字も昔より大きいような気がする。『にほんご』が最初に発刊されたのは1979年。そのころの教科書サイズはA5版だった。『にほんご』もA5版で文字も今の教科書よりずいぶん小さいが、老眼の私が読みづらいことはないので子どもも十分読めるはず。そして何より安野光雅のやさしい絵がセンス良く配置されていて、文章の意味の理解を助けてくれる。文字と空白部分の配分もいい感じだ。それに比べて今の国語の教科書は見ていてせわしない。
この『にほんご』、読んでいて面白いなあと思ったのは、普通の教科書ならば「じを かこう」とか「おおきな こえで よみましょう」と単元の内容を書くところを、「おぼえちゃおう」とか「おもいえがく」と書いていることだ。「うそ」なんて単元もあって面白い。「おぼえちゃおう」には、谷川俊太郎の『ことばあそびうた』の中の「かっぱかっぱらった…」という詩もある。「ごめんね・ありがとう」の単元には、『いちねんせい』(谷川俊太郎・詩/和田誠・絵/小学館)という絵本の中の「わるくち」という詩の一部が書かれている。私は、この詩をペープサートを使って子どもたちに紹介することがあるが、すると子どもたちはいつも笑いながらも不思議な顔をする。悪口をこんなに公然と言っていいのかというような顔で。
『にほんご』の中には、おとぎばなしなどの「お話」がいくつか収録されているのだが、主人公が死んでしまうような残酷な終わり方のものもある。今の国語の教科書にもいろいろな「お話」が掲載されているが、どれもこんな残酷な終わり方はしない。一見、今の国語の教科書の「お話」が良さそうな気がするが、現実の世の中にあふれている「お話」は、そんなやさしいものばかりなのだろうか。テレビのニュース番組やアニメ、ドラマはもちろん、最近は幼児だってネットでゲームをする。そこでは、殺した、死んだ、などの残酷な言葉を聞かない日はない。子どもたちの周りのそんな言葉の断片を、道筋をつけた物語で示してあげることこそ大事なはずだ。
先日SNSで特別支援教育を学んでいる大学生の書き込みを読んだら、彼は障害がある子どもの家庭教師のようなアルバイトをしていて、子どもとコミュニケーションをとるために何をすべきか迷った挙句、週に1回、行くたびに5冊ほどの絵本を読み聞かせるという活動を続けてみたそうだ。すると、子どもは少しずつだが物事のルールに気が付くようになってきたとうれしそうに書いていた。たくさん「お話」を聞くということは、自分をとりまく世界に目を開かせてくれる大切なことなのだ。それには根気よく読み聞かせを続けてくれる大人の存在が欠かせない。
だが、現在は子どもが「お話」にふれることがますます難しくなっているように思う。つい最近、小学2年生の男の子に絵本を読んであげようと思ったら、「ぼく、おはなし聞くの嫌いだ。だって何言ってるかわからんもん」と言われ、ショックを受けてしまった。彼は、小学校に1年以上も通って国語の勉強をしたはずなのに、言葉のおもしろさ、豊かさはもちろん、物語の面白さも知ることなく時がたってしまったのだ。『にほんご』が発刊されて30年。子どもに身近な大人はますます忙しく「お話」をしてあげる時間も無くなり、子ども自身も言葉に興味を持てなくなって、この先どうなってしまうのだろうか…。
 『ことばあそび |
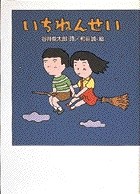 『いちねんせい』 |