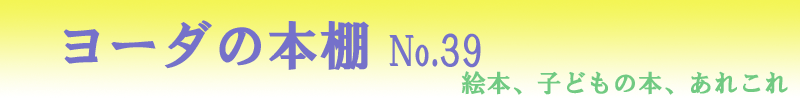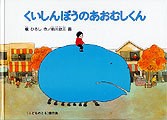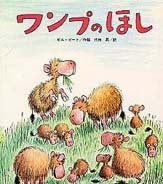ヨーダの本棚No.39(もみの木通信No.39)
2017年1月11日 発行
新年早々、主人と灯油ポンプのスイッチをOFFにしたか、OFFにしなかったかで喧嘩になった。灯油が満杯になると自動で止まるタイプのポンプなのだが、スイッチをOFFにしておかないと何かの拍子に自動でポンプが動いてしまう心配がある。主人は私がOFFにし忘れたと思っているし、私は主人が忘れたと思っている。灯油タンクを挟んで給油のたびに険悪なムード。見かねた娘たちが、「スイッチをOFFにした、しなかったということより、OFFにしたつもりでOFFにされていなかったことの方が問題でしょう。それって認知症の心配があるんでしょ」と一言。夫婦喧嘩は犬も食わぬと言うけど、夫婦そろって子どもたちに老化現象を指摘されるようじゃ、喧嘩なんてしていられませんねぇ。
■近ごろ気になる絵本

『さかだちぎつね』
槙 ひろし 作
前川 欣三 画
福音館書店
|
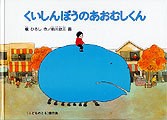
『くいしんぼうのあおむしくん』
槙 ひろし作
前川 欣三 画
福音館書店
|
私の子どもの頃読んだ本の記憶は、いいかげんなようだ。先月の図書館の子どもの本を読む会では、『エルマーのぼうけん』と『エルマーとりゅう』(共にルース・スタイルス・ガネット作 /ルース・クリスマン・ガネット絵 /渡辺茂男訳/福音館書店)を読んだが、子どもの頃に読んだはずなのにストーリーは全然覚えていなくて、でも読み返すとチューインガムにあこがれたことやミカンをやたらと食べることが面白かったことは覚えている。佐藤さとる氏のコロボックル物語シリーズ『だれも知らない小さな国』他4冊(講談社)も家にあったから読んだはずなのに、ストーリーは覚えていなくてフキの葉っぱの下にコロボックルがいるんじゃないかと思ったことだけは覚えている。
大人になっても読んだ本の中身を覚えるのが下手なところは変わらないらしい。最近、絵本について書かれた評論「絵本学講座(1)絵本の表現」(中川素子編・朝倉書店)を読んだ。こういう本は学校の勉強のように一冊一冊ノートを取りながら読む本なんだろうなと思いながらも、ずぼらな私はざっと読み流すものだから内容もあまり心に残っていない。けれど、『さかだちぎつね』(槇 ひろし作/前川 欣三画/福音館書店)という絵本の項目だけは気になった。図書館などで、キツネもなんでもさかさまになってしまう絵本をもう一度読みたいと多くのリクエストを受けた本らしい。30年の年月を経て、文と絵を新たに作り変えて2004年2月の「こどものとも」575号で復刻版がでたらしい。先日ハードカバーのこの本を図書館の棚で見つけたので、小学校5年生の朝の読書タイムで読んでみた。
主人公のたけしはおつかいの帰りに逆立ちをしているきつねにであう。その後も何回か逆立ちをしているきつねに出会うが、話しかけてもきつねたちは知らん顔。ある日、遠足に行くとやっぱり逆立ちをしたきつねが。林の向こうにはさかだちぎつねの村があって、さかだちぎつねは切り株も村も何でも「くるりん ばあぁ くるくる」とひっくり返し、最後には読んでいる絵本までひっくり返さなければならないというストーリー。読み始めはさほど興味のない顔をしていた子どもたちだったが、読み進めると「くるりん ばあぁ くるくる」の掛け声のたびに次はどうなるんだろうと興味津々。自分が真っ直ぐ立っている世界が本当に正しいのか、「さかさま」という概念が何なのか、不思議な世界を感じながら最後まで楽しんでくれた。
なかなか面白い本を見つけたぞ、もっと槙ひろしの絵本が読みたいなと思っていたら、石巻まちの本棚で『くいしんぼうのあおむしくん』(槙ひろし作/前川欣三画/福音館書店)を見つけた。『さかだちぎつね』と同じく、サインペンと水彩絵の具で描かれているが、空の青とあおむしくんの青が印象的な絵本だ。こちらの絵本も1975年に「こどものとも」として発刊され、「もう一度読みたい!」という声に応えて2000年に再発行されたらしい。
主人公のまさおの帽子に小さな穴をあけたのは、くいしんぼうな小さなあおむし。まさおはあおむしくんを飼い始める。パンもチョコレートもペロリ。紙屑までペロリ。町中のゴミをもらってもペロリ。それでもおなかが空いたあおむしくん、町も船も工場も住んでいる人たちもみんな食べてしまう。あっちの国からこっちの国まで残らず食べて、最後はまさおまでペロリ。まさおが気付くと、そこはまさおが住んでいた町のはずれで、あおむしくんのおなかの中には元の世界がすっかりあるという物語。読んで私はギョッとした。このあおむしくん、何かを暗示しているような気がしたからだ。
最初はかわいいあおむしくん、食べ過ぎて怒られると「ぼく もう ぜったい まちなんか たべない」と誓うのに、やっぱりだめで食べ始めると止まらない姿は、人間の力では制御できなくなった原子力発電所じゃないか?それだけではない。最近AIやIoTなどの言葉をよく耳にする。自動運転の実用化が近いとか、漫画やSF小説に登場するロボットのようなものが作られるのも時間の問題のような報道がされているが、そのように社会が高度にコンピューターに制御される時代になったとき、私たちはコンピューターに制御されていることが分かるんだろうか。あおむしくんのように人工知能はゴミ問題も公害問題も飲み込んで解決してくれる頼もしい存在かもしれないけれど、いつか私たち人類までも飲み込んで、青い空の下に住んでいると思っているけど、本当はあおむしくんのおなかの中のような人工知能が作った青い世界に住んでいるかもしれない。
何かを暗示するといえば、息子が小さい時に何度も読んでと言って持ってきた絵本『ワンプのほし』(ビル・ピート作/代田昇訳/佼成出版社)を思い出した。とても気立ての良い草食動物のワンプたちは一面を緑に覆われた小さな星にのんびりとくらしていたが、ある日バッチイ星からやってきたバッチイ人に星をのっとられてしまう。地下に逃げて細々と暮らすワンプたち。バッチイ人たちは、ワンプの星を開発してコンクリートの町を作り、大気も町も公害で汚染され暮らせなくなると新しい星を探して空の彼方へ飛びだっていく。地上が静かになり恐る恐るワンプたちが外に出ると、そこはコンクリートに覆われた廃墟。ガラクタやごみの中を何マイルもさ迷うワンプたち。ワンプたちはあきらめて地下に戻ろうとすると、緑の草原の一部が残っていて希望がわいてくるという結末。カピバラを思わせるワンプたちがやさしい色合いで描かれているのに、自然破壊や公害問題などがテーマになっていて、読むたびになんてディープなんだろうと思った絵本だ。
たぶん、子どもたちは絵本の中に社会問題が暗示されているなんて思わないで読んでいるんだろうと思うが、そのテーマは心のどこかに残っていて欲しいと思う。最近『この世界の片隅に』(片渕須直監督・こうの史代原作)が話題になっている。広島県の呉を舞台に第二次世界大戦の戦火が激しくなっていく中で生きた人々を描いた映画だが、めずらしく息子がFacebookで人に勧めていた。社会問題などには興味がないのかと思っていたが、少しは世の中のことも考えていたのかとうれしく思った。これはきっと、幼い頃にいろいろな絵本に触れて育ち、知らず知らずのうちに社会を思う感性を身に付けたに違いないと勝手に思うバカな母親であった(笑)。
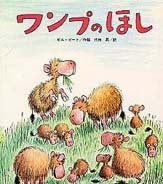
『ワンプのほし』
ビル・ピート/作
代田 昇/訳
校正出版社
|
Copyright (c) Yoda Harumi, 2017 All Rights Reserved.