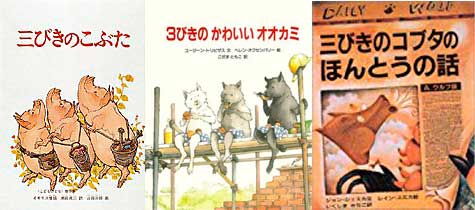2016年11月11日 発行
先日、川の上・百俵館に行ったら薪ストーブが取り付けられていて、ちょうど初めてストーブに火を入れるところだった。薪ストーブは火おこしが大変そうだなと思っていたが、意外に簡単に火がついて、火力調整もレバーでできるし、灰の処理も簡単にできるらしい。炎を見ていると、なんだか癒されていい気持ち。薪がはぜる音もいい。ドイツを中心にヨーロッパに広まっているシュタイナー教育では、幼児の火の体験を大切にしていて、軽食をとるときや昔話を聞くときはろうそくを灯すらしい。寒い季節、薪ストーブの炎の横で本が読めたらどんなにいいだろう。 我が家にも薪ストーブが欲しいなと思ったが、なんでも煙突工事が大変らしい。人と環境にやさしい生活がコスト面でも優しくなってくれるには、しばらく時間がかかりそうだ。地球環境には悪いけれど、我が家は石油ストーブで我慢かなぁ。
■昔話で遊んじゃえ!
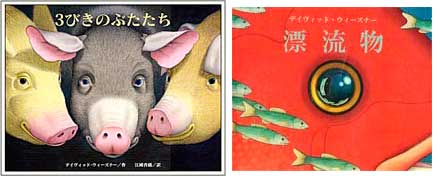
㊧『3びきのぶたたち』
デーヴィド・ウィーズナー さく/江國香織 訳/BL出版
㊨『漂流物』デーヴィド・ウィーズナー さく/BL出版
10月の石巻図書館の「子どもの本を読む会」のテーマはアメリカの絵本作家、デーヴィド・ウィーズナーの絵本だった。
デーヴィド・ウィーズナーは、3回コルデコット賞を受賞しているアメリカの絵本作家だ。コルデコット賞とは、アメリカで出版された最もすぐれた絵本に毎年贈られている賞で、19世紀のイギリスの絵本作家ランドルフ・コルデッコトにちなんで名づけられたもの。ウィーズナーは、1992年に『かようびのよる』(徳間書店)、2002年に『3びきのぶたたち』で、2007年に『漂流物』(BL出版)と3回コルデコット賞を受賞している。3回も受賞しているのは、今のところウィーズナーを含めて二人(もう一人は、『三びきのやぎのがらがらどん』(福音館書店)の作者マーシャ・ブラウン)しかいないので、すごい作家らしい。
最初、「この本面白いよ」と教えてもらったのは『漂流物』だった。この本は題名と作者名以外は文字の無い絵本だ。文章はないけれど、詳細に描かれた絵が、海岸に流れ着いた古い水中カメラを拾ったことから始まる不思議な世界を饒舌に物語ってくれている。
デーヴィド・ウィーズナーの絵本は、『漂流物』のように文字の無い絵本が多い。コルデコット賞を受賞したもう一冊の絵本『かようびのよる』も文字が少ない。が、『3びきのぶたたち』はちょっと雰囲気が違う。始まりはイギリスの昔話“3びきのこぶた”の物語のようで、わらや木、レンガで家を建てたブタたちはオオカミに家を吹き飛ばされる。だが危ういところで逃げ出すのだが、そこは絵本の外の世界で、その後は3匹で紙飛行機に乗ってわらべうたやおとぎばなしの世界に行ってしまう。
“三びきのこぶた”の物語は、イギリス昔話だ。作家ジョセフ・ジェイコブズがイギリスに伝わる昔話を子どもたちに聞かせ読ませるためにわかりやすく書き直して1890年に刊行したEnglish Fairy Talesという本の中に収められていて、この本によりイギリスに広まったという。このジェイコブズの本の物語を忠実に訳したのが『三びきのこぶた』(瀬田貞二訳 山田三郎画 福音館書店)だ。この話では、1匹目のブタと2匹目のブタはオオカミに食べられてしまうが、3匹目のブタは知恵をしぼってオオカミから逃げ、最後には煙突から降りてきたオオカミを大鍋でコトコトと煮て晩御飯に食べてしまう。けれども、最近の日本の絵本やお遊戯会の劇では、このジェイコブズのストーリーは残酷だという理由で、コブタはみな生き残っていたり、オオカミがレンガの家を吹き飛ばそうとする場面以降の物語が省略されていたり、最後にはコブタとオオカミが和解するようになっているらしい。小学校の読み聞かせの時間などで、私はよく瀬田貞二訳の『三びきのこぶた』を読むのだが、「ふふの ぶっと、いえを ふきとばして、こぶたを たべて しまいました」と読むと、子どもたちは必ず「え~、食っちゃうの?」と驚くが、残酷さも弱いブタが生き残るための当然の行為と感じるようで気にせずに最後まで聞いてくれる。
ところで、デーヴィド・ウィーズナーの『3びきのぶたたち』もブタたちはオオカミに食べられないし、最後はみんな仲良くなるが、こちらは残酷だからというより、むしろみんながジェイコブズのストーリーを知っているのが前提で、お話で遊んでいると言った方がいい。奇想天外なストーリーは、ちょうど幼稚園児がテレビ番組を見て、それを話してくれる時のようだ。
“三びきのこぶた”のパロディ絵本と言えば、『3びきのかわいいオオカミ』(冨山房)も衝撃的だった。こちらは、オオカミとブタの立場が逆転して進んでいく。『三びきのコブタのほんとうの話』(岩波書店)は、オオカミ側からこの昔話を検証している絵本。「もしも チーズバーガーが かわいかったら、それを たべる にんげんだって きっと わるい やつだってことになると おもうよ。」とブタを食べたことを正当化しているオオカミを笑える余裕を持って読みたいなと思う本だ。
いずれにせよ、もとのおはなしを楽しんで大きくなった子どもたちだからこそパロディ絵本は楽しめる。ラボ・パーティの時間にウィーズナーの『3びきのぶたたち』を読んだことがある。最初は「なんだ、“三びきのこぶた”の話か」と言っていたが、途中から様子が違うことに気が付いて絵本に釘付けに。ちょうどブタたちが紙飛行機で飛んで行った先で入り込む場面では、その場面のもとになっているマザーグースを楽しんだ後だったので、興味津々立ち上がって身を乗り出してきた。ところが、この本の最後は子どもたちが知らないドラゴンのおとぎ話のパロディになっていて、そのページになると、さっきまでの興味はどこへいったのやら、「ドラゴンの出てくるおはなしって何?」といってみんなどこかへ行ってしまった。パロディ絵本は、元の物語をよく知っていないと楽しめないらしい。
昔話は時代によって変わっていくものだ。「桃太郎」も、江戸時代の赤本や明治初期の縮緬本とよばれた絵本では庶民の娯楽であった歌舞伎の影響が濃かったが、戦時下に出版された絵本は植民地化とのダブルイメージで描かれた内容に変化し、それが今の典型になっているという。“三びきのこぶた”も、大人の都合で変化させるのではなく、変化するなら子どもたちの欲求に応じて変化して欲しいと思う。パロディ絵本も楽しめる余裕を持って。