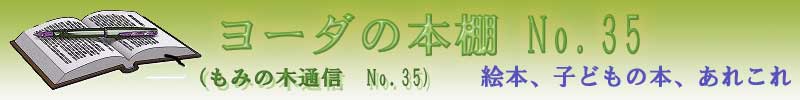
2016年6月20日 発行
あんまり左膝が痛いので病院に行ったら、鵞足炎と診断された。先生には、「運動しても大丈夫。1週間もすれば治るから」と言われて安心して家に帰った私。けれども、薬を飲んでも湿布を貼っても痛みがとれない。1週間たったが、まだまだ歩くのが大変。困ったな、これは何か特別な病気なのかも…なんて心配していたら、2週間たって、ようやく痛みが取れてきた。ケガというものは、若い人は治りが早いけど、年齢を重ねるにつれて治りが悪くなるらしい。私ももう若くないのね。中高校生に負けたくないとランニングを始めたけど、体は確実に年をとっている。病院の先生も「もっとゆっくり走る量を増やしてね」と言っていたもんね~。
■絵を読む楽しさ
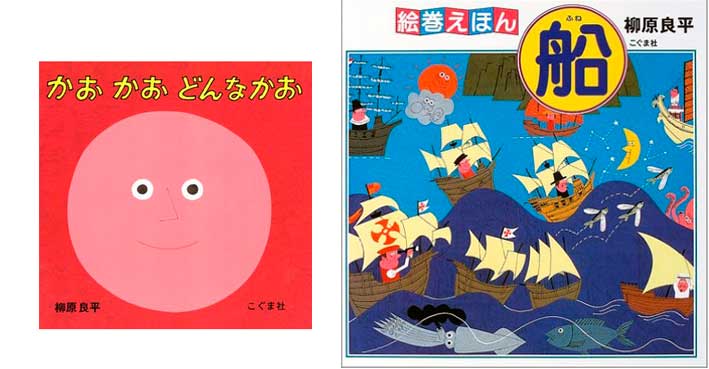
㊧『かおかおどんなかお』㊨『絵巻えほん 船』
柳原良平 作
こぐま社
5月の子どもの本を読む会のテーマ、柳原良平さんの絵本といえば、ページをめくるたびに赤ちゃんの大好きな「かお」があらわれる『かおかおどんなかお』(こぐま社)が有名だが、この絵本の作者、柳原良平さんは、若いころはサントリーに社員として長年勤めていて、トリスウィスキーのCMキャラクター「アンクルトリス」の産みの親なのだそうだ。子どもたちや若いお母さんにトリスおじさんなんて言っても「?」という顔をされてしまうが、子どもの本を読む会に参加しているメンバーは全員「あ~、あれね」と分かってしまった(笑)。
さて、柳原良平さんは無類の船好きで、『ぼくふねにのる』(佼成出版社)など、船を描いた絵本やイラストもたくさんある。そんな中でも、面白いと思ったのは、『絵巻えほん 船』(こぐま社)だ。この絵本は細長い紙を屏風状に折りたたんで作られていて、左から順に丸木舟や筏、帆船、現代の大型タンカーや豪華客船まで、いろいろな船が時代順に描かれ、変化していった様子が一目瞭然でわかる。それらの絵は、それぞれの絵は細部まで細かく描いているわけではないのだが、特徴をとても良く描いていて、文章による説明はひとつも無いのに、饒舌に船の歴史と特徴を物語っているのだ。きっと、乗り物好きの男の子は、部屋一杯にこの本を開いて、飽きることなくいつまでも眺めているだろうなと想像すると、こちらもうれしくなってくる。
こんなに船好きの柳原良平さんだが、意外にも、海のそばで船を見ながら育ったわけではないそうだ。遠くはなれているからこそあこがれが強くなることも多いものだ。海や船へのあこがれが、いろいろな船への興味となり、こんなステキな絵本を生み出したと思うと、どこへでも簡単に行けて簡単に見られるということが、必ずしもいいというわけではないのだなと思う。
ところで、歴史を描いた本と言えば、『絵で見る日本の歴史』(西村繁男文・絵 福音館書店)がある。この本、絵本専門士養成講座の講義で、絵本学会会長の松本猛先生から教えていただいた絵本で、石器時代から順に縄文時代、弥生時代、古墳時代…現代の広島の町を空から眺めた景色まで、その当時生活していた人々の様子や街並みなどの風景が細部にわたり描かれている大作だ。先生の講義でもおっしゃっていたが、西村繁男さんがこの絵本の細部を描くためには、大変な量の資料を調べただろうし、想像力も働かせただろう。私たち大人も子どもたちも、歴史を学ぶと言うと、年号や人物名を覚えることになっているが、本当に歴史を知るということは、その当時の無名の人々がどんな暮らしをおくっていたかを知ることではないのか。この絵本は、それを伝えるために描かれたのではないだろうかと。
この絵本、平安時代の御屋敷の塀の外でご主人を待っている使用人の手持ち無沙汰な様子とか、港で会話する耳の遠いおじいさんまで描かれている人々は多彩だ。おまけに、時代考証がきちんとされていて、その証拠に、平安時代には屋根の上にさりげなく猫が描かれていたり(猫は平安時代に渡来した)、ポストの色も明治初期は黒色だけど、大正時代には赤色になっていたりする(日本のポストが赤になったのは明治41年)。本当にこの絵本、順番にページをめくって変化を楽しむのもいいし、特定のページを細部まで見るのも楽しい。
西村繁男さんというと、『やこうれっしゃ』(福音館書店)の作者だ。この絵本には、かつて上野駅から金沢駅まで走っていた急行「のと号」に乗り合わせた人々の様子が描かれている。息子が小さなころ図書館で見つけてきて、親の方がなつかしいなあ、とうれしくなった絵本だ。4人掛けの座席に足をあげて寝ている様子なんて、私たちもあんな風に少しでも快適に寝ようとがんばったよなとなつかしい。西村繁男さんは、『やこうれっしゃ』を書いたころの作品を観察絵本と呼んでいるそうだ。今の時代は全てが忙しくて、何かをゆっくりと観察することがないが、だからこそ、この絵本に子どもも大人も惹かれるのかもしれない。
いつまで見ていてもあきない絵本といえば、ピーター・スピアの絵本がある。ラボの子どもたちと、「ロンドン橋おちた♪」という歌詞で有名なマザーグースでよく遊ぶのだが、その歌を本にした『ロンドン橋がおちまする!』(渡辺茂男訳・ブッキング)は、一目見て、なんてステキなんだろうとほれ込んでしまった。
日本では、「ロンドン橋おちた♪おちた♪おちた♪…」と歌う1番目の歌詞しか歌わないが、この歌、続きがあって、橋のかけなおしがされるのだが、その材料が木と粘土から鉄になり石になり、最後に金と銀になって、それでは盗まれるから見張り番をたて番犬をはなし…と話が続いている。絵本はその歌のストーリーに従って絵が描かれているのだが、なんと!ロンドン橋には家が建てられ人々が住んでいるのだ。女の人が窓からバケツの水を捨てていたり洗濯物が干されていたり、おまけに文房具や刷毛を売る店もあるし宿屋まであって、橋の上にこんなにたくさんの物があれば、どんなに立派な橋をかけても橋が落ちるよなと思ってしまう。はたして、これって本当のことだったの?と疑ってしまうが、本当だったようで、1762年までは人が住んでいたらしい。そして、1831年に新しい橋が完成し、この絵本に描かれている古い橋は取り壊されてしまったのだそうだ。
この絵本、幼児には案外喜ばれず、小学生ぐらいの子どもたちだと面白がってくれる。私は時々、近所の小学校に絵本の読み聞かせに行くが、そういう時の絵本は絵がはっきりと大きく、誰もが好むようなものを選ばざるを得ない。今回取り上げた絵本のような、時間をかけて、近くでゆっくり見て楽しめる絵本こそ子どもたちに見て欲しい本なのに、一番面白がってくれる小学生に紹介する機会が無いのは、とても悲しいのだが…。
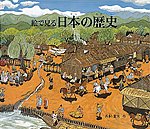 『絵で見る日本の歴史』 |
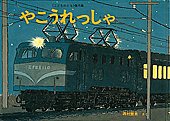 『やこうれっしゃ』 |
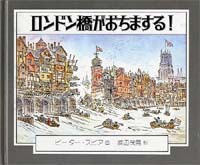 『ロンドン橋がおちまする』 |