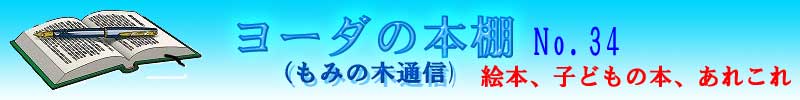
2016年4月26日 発行
熊本をはじめとする九州で大きな地震が発生し、一週間が過ぎました。メディアの伝える映像や写真に、ことの重大さを感じます。被害にあわれた方々へ、ご冥福とお見舞いを申し上げます。私も5年前の東日本大震災で被災し、いろんなことがありました。そこで、子どもの本を読む会のテキストをはなれ、震災での私の体験などを書いてみます。過去の体験を教訓に、今を行動することは大事なことですからね。
■流言飛語
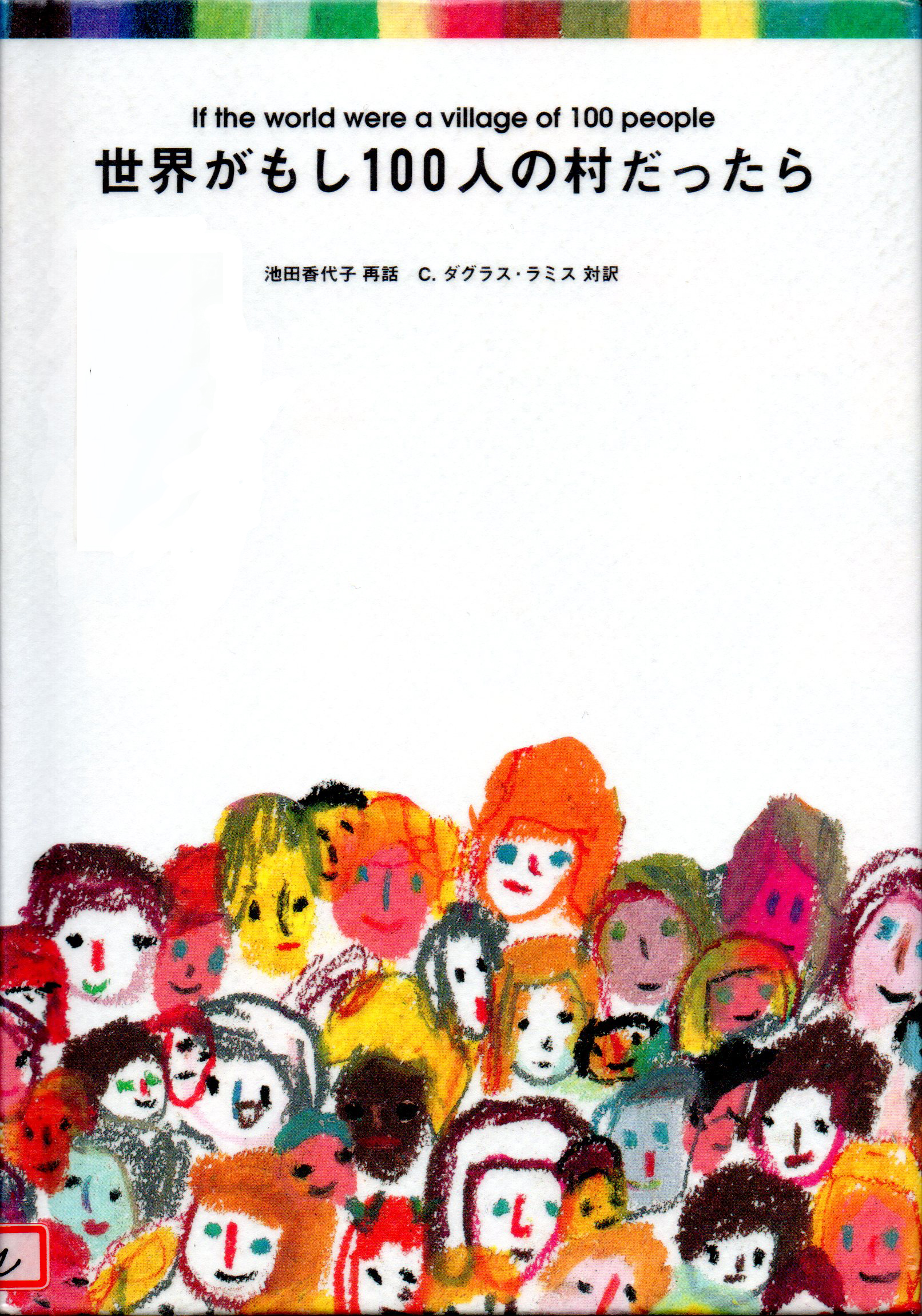
『世界がもし100人の村だったら』
池田香代子 再話
C・ダグラス・ラミス 対訳
マガジンハウス刊
東日本震災大震災から5年たったが、震災直後の自分の行動で後悔していることがいくつかある。一つは、地震発生の直後、安全な自宅から車に乗って学校にいる上の子どもたちを迎えに行こうとしたこと。家にいれば津波にあうこともなく、末娘に怖い思いをさせずに済んだし、愛犬や車だって無事だっただろうし…と、時々ふと思い出し、胸が苦しくなる。もちろん、そんな行動をした私のことを、家族も親戚もだれも責めるわけではないのだけれども。まあ、こう言いながらも、私の場合は、被害は笑い話ですむ程度だったし、だからこうやってこのことを冷静に文章にできるのだけど、被害の大きかった方たちが気持ちの整理をするためには、まだまだ長い年月が必要なのだろうと思う。
そしてもう一つの後悔は、何の疑いもなくデマを信じてしまったこと。確か、津波発生から何日かたって町の被害の様子が少しわかってきたころのこと。多くの人が家族と再会し、けれど、中央からの支援物資などは届かず、ご近所で物資を譲りあっていたころのことだ。水道が復旧していないと給水所が町の情報交換場所となる。私がペットボトルに水をもらって帰ろうとすると、知り合いに声をかけられた。「外国人の窃盗団がうろついているから、近所のみんなに戸締りをしっかりするように伝えて。外国人だというのは見ればわかるって話だから」と。泥棒が出没しているというのは聞いていたし、津波の被害にあった私の車も知らないうちにガソリンが抜き取られていた。それに知り合いの安否を訪ねて市の中心部まで自転車で行ったときにも、コンビニエンスストアのガラスが割れていたのを目撃している。これは大変だ!早速みんなに伝えなくっちゃ!と思った私。この情報を家に帰って家族に伝え、なんとご近所さんにまで伝えに行った。「あの〜、聞いた話なんですが、外国人の窃盗団がうろついているらしいので、戸締りをしっかりして下さいとのことですよ」そこまで言って、ふと我に返った私。あれ?何で外国人なの?もしかして、これってデマ?
冷静に考えれば、窃盗団が外国人と限定されるのはおかしい。そもそも窃盗団がいたのかも疑わしい。津波にあって動かない車からガソリンを抜くのは仕方のないことだろうし、コンビニのガラスだって地震で割れただけかも。それに、見れば外国人ってわかるというのもおかしな話だ。よりによって外国人と接する機会の多い仕事の私が、こんなデマを広めてしまったなんて…。関東大震災の時に朝鮮人が襲ってくるという流言が虐殺事件を引き起こしたという話を日本史で習っていたじゃないか。オイルショックの時のトイレットペーパーを買い占めるテレビの映像も、家族で「何をやってるんだか…」と冷静に見ていたじゃないか。ああ、私は何を勉強してきたんだろう…。我に返ったあの時のショックは、5年たった今でも忘れられない。
非常時は情報が誤って伝わりやすいものである。私自身の安否も後日、「依田さんって、津波にあって、内海橋の真ん中で一台だけ残った車に乗っていて助かったらしいって聞いたよ」と知人に聞いて、私本人が思いっきり驚いたことがあった。内海橋は北上川の河口近くにかかる橋で、津波により倒壊こそしなかったが船やガレキが積みあがっていた橋である。一台だけ車が残るなんてそんなドラマのようなことがおきたとは思えない。そもそも、私が津波にあったのはそこから3キロほど内陸だ。まあ、震災直後は停電が続き、さらに電波の状態も悪く、おまけに携帯電話が水没して使えなかったのだから、情報が正確に伝わらなかったのは仕方がない。しかし、どんな流言も、まるで昔話や都市伝説のように変化して伝わるというのは面白い現象だと妙に感心してしまう。私が助かった話は困ったことではないのだし、笑い話になってみんなの心が和むのなら、面白おかしく伝わっても仕方がないか。
ところで、こんなデマや噂話が流れる一方、震災直後の電波の悪い中、いろいろな人たちとの情報のやり取りで役立ったのは、高校生だった長女の携帯電話のメールだった。メール以外にもツィッターなどのSNSが注目されたのが東日本大震災だったと思う。メールやツィッターでも、たくさんデマが流れたが、役に立つ情報もたくさん得られたことは間違いない。東日本大震災から5年たち、今ではタブレット端末やスマートフォンが普及して誰もがSNSを簡単に使えるようになった。熊本を中心とする今回の地震では、SNSを通じて有益な情報がたくさん被災地の届けられるだろうと思うし、支援もより良い方法で届けられると思う。なぜなら、いろいろなメディアを通して、過去の教訓が生かされていると感じること多いからだ。先日、ジャーナリストの津田大介さんがラジオで、「SNSではデマが流れることが多いので、リツイートやシェアする前に、以前の発言を参照して信用のおける情報かどうか確かめてからシェアしてほしい」と話していた。5年前は、ラジオでそんな情報は聞かなかった。
インターネットといえば、Eメールで次から次へと書きなおされたり付け加えられたりして世界的に流布した文章から生まれた絵本『世界がもし100人の村だったら』(池田香代子、C・ダグラス・ラミス再話/マガジンハウス) がある。世界の人口63億人を100人の村に縮め、人種、経済状況、宗教など人口比率をあらわした絵本だ。例えば、男女比は女性が52人で男性が48人、人種は57人がアジア人で21人がヨーロッパ人、14人が南北アメリカ人、8人がアフリカ人という具合。この文章は2001年ぐらいからインターネット上で話題になり始め、今では動画にもなってもいる。(参考https://www.facebook.com/GOODHQ/videos/10153453652588059/)
データとしては、ネット上の動画の方が最新だが、絵本の方は最後の文章がいい。これを読むと、自分がいかに幸福であるか、そして世界のために自分は何か行動をしなければと真摯に思う。だけど何をしなければならないかは、この本の中に答えはないので、自分で考えなければいけないが…。
考えるというのはとても辛い作業だ。普段の生活では考えなくても何となく生活できてしまうが、非常時は考えて行動しなければとんでもないことになってしまうことも多い。今回の地震は、5年たって考えることを忘れかけた私に、もう一度考えろと言っているのかもしれない。
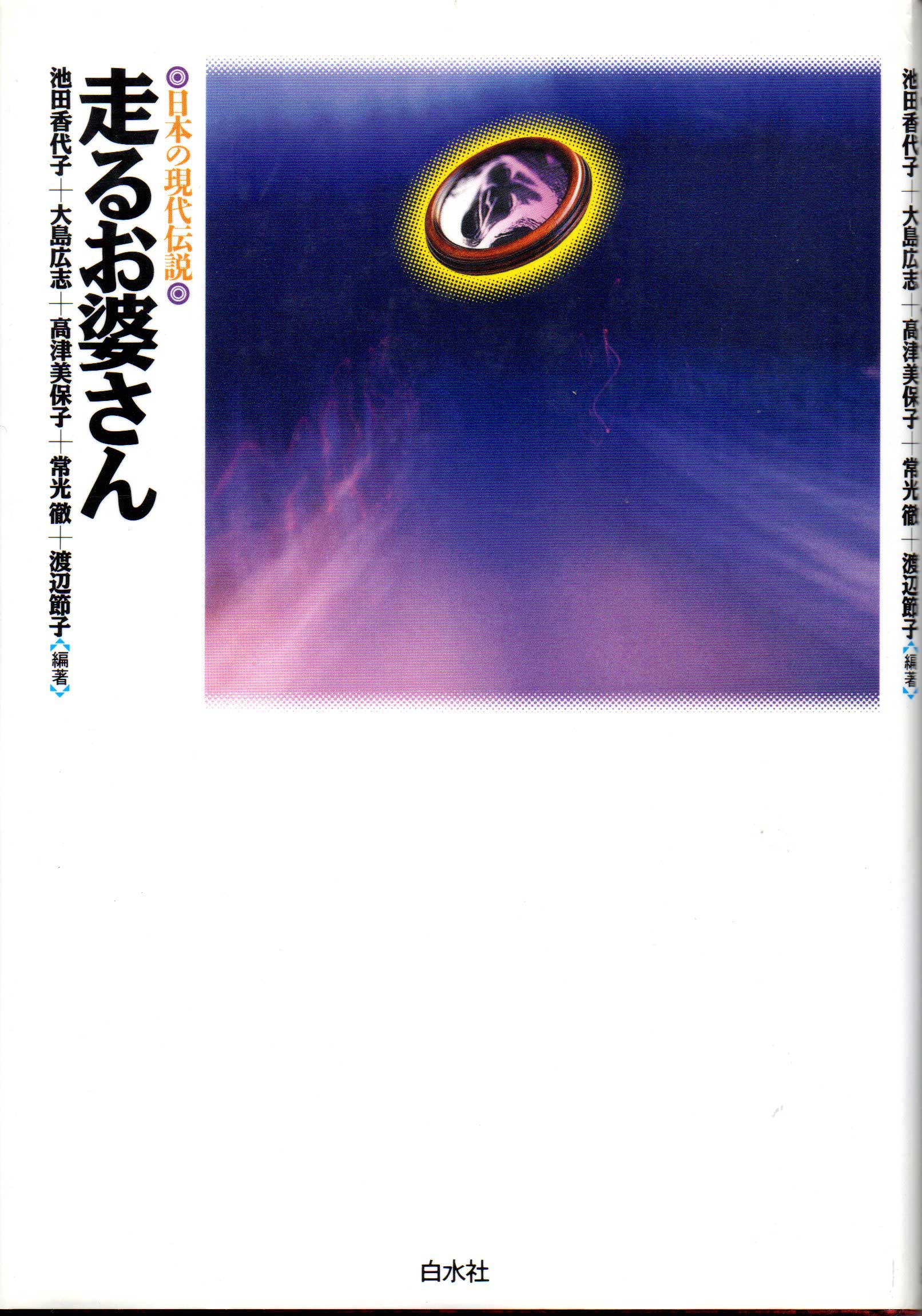
『走るお婆さん―日本の現代伝説』
池田香代子, 高津美保子,渡辺 節子,
大島広志, 常光徹著(白水社)
口裂け女の話のような、口伝えで広がった怖くて怪しい都市伝説などと言われる現代のフォークロアを集めた本。1997年に石巻図書館で借りて読んで、ものすご〜く印象に残っていたので、ここに載せようと思い蔵書検索してみたら無くなっていた。貸し出された先で津波にあい流されたのか、それとも…。
Copyright (c) Yoda Harumi, 2016 All Rights Reserved.