
2016年1月9日 発行
2016年、新しい年が始まった。今年は申年。テレビやスーパーの折り込みチラシなどで、赤い下着で新年を迎えると縁起がいいとコマーシャルをしている。主人も暮れに、赤い歯ブラシも縁起がいいらしいと買ってきていた。
赤い下着の言い伝えは、随分昔からあるらしい。そう言えば私も子どもの頃、母が、「近所のおじいさんが『今日は申赤で、昔は赤褌を付けたけど、今どき褌を付けないから、赤いパンツを穿いているんだ』と自慢げに言っていた」と大笑いしていたことがあったのを思い出す。
核家族化も進み、ご近所さんで井戸端会議をすることも少ない現代、昔の言い伝えが人から人へ言葉で伝わるのではなく、販売促進のためにメディアを通じて広がっているというのは、なんだか変な感じがするのだが…。
■初めての推理小説
〜石巻市図書館・子どもの本を読む会 12月テキストに寄せて〜
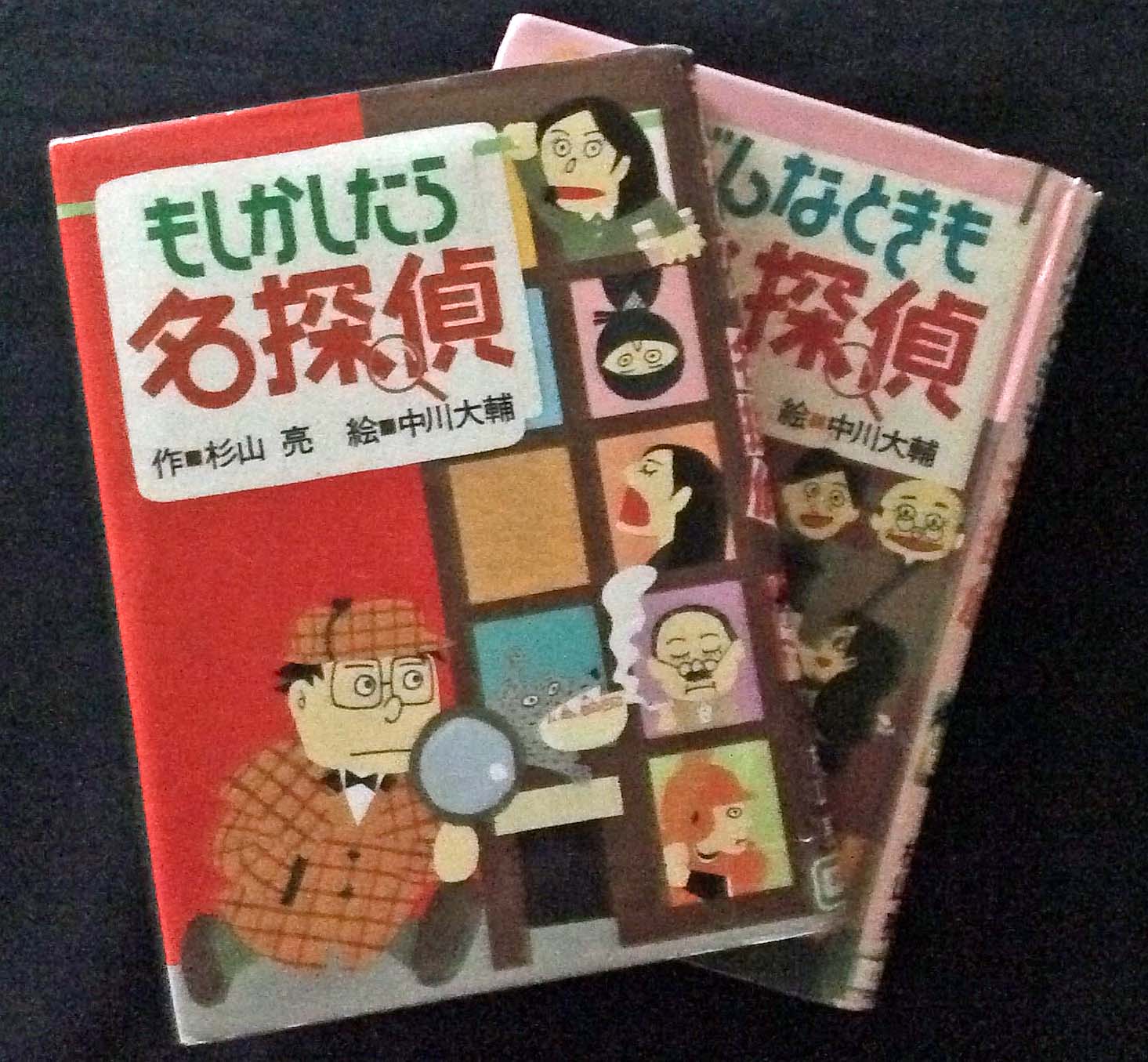
「ミルキー杉山あなたも名探偵」シリーズ
杉山亮 作・中川大輔 絵・偕成社
子どもの本を読む会では、翌々月に開かれる会のテーマをみんなで考える。これが、結構大変だ。さて、次のテーマは何にしよう?と毎回みんなで悩む。先々月も悩んでいると、「秋は推理小説の季節」という雑誌の見出しが目についた。そこで、推理小説をみんなで何冊か考えてみるが、どれも思いつくのは比較的分厚い本ばかり。もっと気軽に読める推理小説ってないのかしらと悩んでいたところ、担当の司書さんが、「この本はどうでしょう?」と持ってきた。みんな見た瞬間、「うん、これいいですね」。
ちょっと厚い本を一人で読んでみたいと思う子どもにちょうどいい厚さと文字の大きさのこのシリーズ。主人公は探偵のミルキー杉山という、小学生と幼稚園児の2児を育てるお父さんだ。このミルキー杉山、探偵では家族を養えないので、いつもバイトをし、奥さんとは訳あって別れて暮らしている。別居しているといいながらも、住んでいるところも近いし、奥さんも事件解決に協力するし、ミルキー杉山も奥さんが大好きなようだ。私たちおばちゃん読者は別居の理由が気になるが、理由はどの巻でも語られていない。その他にも石頭けいぶ、怪盗ムッシュ、探偵仲間ボウズすすきだ、ツルまつのなど、楽しいネーミングの登場人物がたくさん登場し、いろいろな事件が起きる。けれども、どの事件も暴力的な事件ではないので安心して読める。1冊の本の中には2〜3の事件が収められ、それぞれ「事件編」と「解決編」に別れている。「事件編」を読んで犯人はだれかよく考えてから「解決編」を読みましょうということらしい。読んでと言いながらも、「解決編」の文章にだけに事件解決のヒントがあるわけでなく、絵が重大なヒントになっていたり、町の地図を見ながら考えなければならなかったり、時には暗号を解いたりと、テレビのクイズ番組のようでなかなか楽しい。
私の子どもの頃は、推理小説といえば江戸川乱歩の怪人二十面相とか、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズのシリーズとか、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズが学校図書館に並んでいて、順番に借りて読んだことを思い出す。けれども、今は小学校の図書室にそれらのシリーズはあっても、子どもたちが借りている様子が感じられない。ある日、娘たちが某テレビアニメを見ていた時のこと、登場人物の名前は推理小説の作家の名前に由来することを主人と私二人で説明したことがあった。その時も、娘たちにはピンとこない様子だった。娘たちに「推理小説読まないの?アガサ・クリスティとか知らないの?」と私が聞けば、「赤川次郎とか読むよ」と返答。ああ、時代が変わったんだ、自分が子どもの頃に読んで面白かった本を今の子どもたちに勧めるだけでは、子どもに本を読んでもらえないのだと感じた瞬間だった。
ところで、「ミルキー杉山あなたも名探偵」シリーズ、1作目の『もしかしたら名探偵』が1992年に発刊されて以来、次々と続編が出ていて、最新刊『ふりかえれば名探偵』は、昨年5月に発刊されている。メイド喫茶風のお店が事件の舞台だったり、作家の限定色紙が狙われたり、世の中の話題を組込んでお話が作られているのも子どもたちに人気の理由なのだろうと思う。司書さん曰く、「けっこう、子どもたち借りていきますよ」というのも納得できる。何気なく、このシリーズの古い刊を手に取り、裏表紙をめくってみると、図書館がコンピューター化される前に使用されていた貸出日時を記録する用紙がのり付けされたされたままだった。そして、そこには日付印が沢山押されている。中には一枚で足りなくて、貼り重ねたものまである。いかに子どもたちが読んでいるか一目瞭然だ。
今では、公共の図書館の本はもちろん、学校図書にもバーコードがついていて、貸出手続きはパソコンでバーコードを読み取れば終了だが、かつて石巻図書館では、本の背表紙の裏に本の名前などが書かれたカードが入った小さな袋が付いていて、貸し出しの際には、その袋の中から図書館職員がカードを抜き取って管理し、本に貸出日時を記録するという方法だった。学校図書館などは、図書委員が図書カードに一冊ずつ借りる本の分類番号や題名などの情報を書き込んでいったものだ。そういえば、柊あおいの少女漫画を映画化したスタジオジブリの『耳をすませば』の主人公・月島雫が天沢聖司と出会うきっかけは、自分が借りようとする図書館の貸し出しカードに必ずその名前があったからだったっけ。そんなステキな出会いも、バーコードを「ピッ」じゃ、おこりえない。
とはいえ、図書館の貸し出しシステムが今のようになったのは、利便性とプライバシーの問題があったらしい。読む(選ぶ)本には、多かれ少なかれその人の思想や考え方が反映する。他人に読んだ本がわからないようにという配慮が必要だ。他人には解らないとはいえ、ネット書店ではトップページを開くたびにお勧めの本の画像が出てきて次々と買いたくなるが、何だかネット書店に自分の心の中を見透かされているようで気持ちが悪い。利用者を増やすことが大事でも、図書館は絶対にそうならないで欲しいと思う。
推理小説に話を戻すが、江戸川乱歩の作品は、戦時中は発禁処分になっていたそうである。犯人のトリックを見つけ出す探偵が時の政府を糾弾するわけでもあるまいし、なぜ?と不思議に思うのだが、一人の人間の死の理由をあらゆる角度から捜査し解明するということは、人間の命を尊重しているからこそ行う行為だ。怪しいと思ったら理由は何であれ連行しようとする政府にとって、些細な事件でも、物理的証拠を検証して正しい犯人を見つけ出す探偵が人気を得るのは、法律を無視した国家には気に食わないはずだ。
今の日本は、好きな本が好きなだけ読める。これからも、子どもたちには好きな本を好きなだけ読んでもらいたいし、政府はそうであるように努力して欲しい。決して有川浩の『図書館戦争』(メディアワークス刊)のような事態がおきないように…。
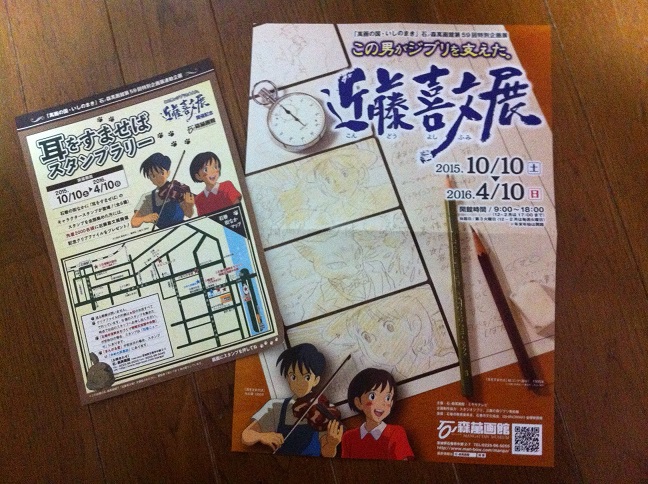
石ノ森漫画館では、
『耳をすませば』の監督 近藤善文展が行われている。
2016年4月10日まで
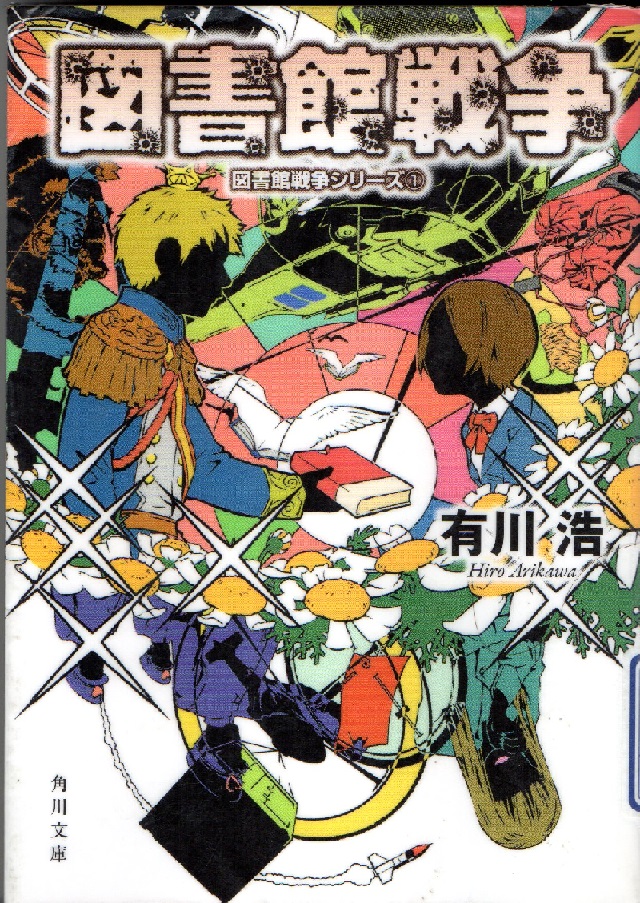
『図書館戦争』文庫版
有川浩作・角川文庫
ハードカバーはメディアワークスより発刊。ライトノベルとか、YA(ヤングアダルト)文学と呼ばれる分類に入る小説。
Copyright (c) Yoda Harumi, 2016 All Rights Reserved.