
2015年12月4日 発行
例年よりも暖かいとはいえ、庭に出ると雪虫が飛んでいる。学校から帰ってくる子どもたちも、「ゆきんこ飛んでたから、そろそろ雪ふるんじゃない?」と言って家に入ってくる。寒さ知らずの子どもたちには、ゆきんこは初雪を知らせるうれしい存在のようだが、冷え性の私にとっては、辛い季節の到来を知らせる虫。雪は嫌だなと思いながらも、季節は師走。クリスマスだけは雪になって欲しいと思うのは、どうしてかしら?
■芝居の原作を読む
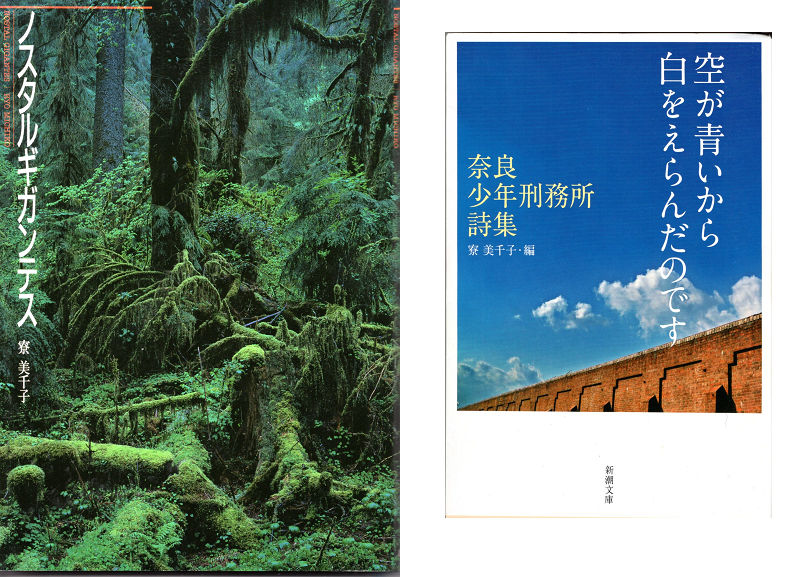
㊧『ノスタルギガンテス』
寮美千子作・パロル舎
㊨『空が青いから白をえらんだのです
―奈良少年刑務所詩集―』
寮美千子編・新潮文庫
先日、Tama+ project、ココロノキンセンアワー主催の芝居、「ノスタルギガンテス2」(原作 寮美千子)をN’s Squareというライブハウスに観に行ってきた。昨年の夏の終わりごろに同じ会場で行われた「言葉の海へ」(原作 高田宏)というジャズピアノの生演奏付きの朗読劇が面白かったので、またお芝居が観たいと思ったからだ。前回は、一関出身の一人の学者、大槻文彦が日本最初の本格的国語辞典を作り上げていく過程を描いた作品。一方、今回は詩人の寮美千子さんの小説『ノスタルギガンテス』(パロル舎刊)を劇化したもの。もちろん原作も演出者も役者も違うので、違う芝居になるのはあたりまえなのだが、あまりにも違いすぎて、どうしても原作が読みたくなって本を買って読んでみた。
主人公の小学生、草薙櫂は、ある日、缶と青いガラス瓶のかけらで作ったメカザウルスを、ママに燃やせないゴミといっしょに処分されてしまう。メカザウルスをゴミ置き場から拾ってきた櫂は、マンションのそばの公園の一本の木に括り付けた。すると、その木には、次から次へとキップルが括り付けられていく。キップルとは、他人から見るとガラクタだが、括り付ける人の思いがつまった「役に立たなくてもとてもすてきなものたち」だ。撤去しても撤去してもキップルは括り付けられ、木の周りにも置かれていく。それは、一つの社会現象となり、ある日現れた命名芸術家と名乗る男と、櫂がカメラ男と呼ぶ写真家の行動によって、櫂の思いとは別に、櫂は少年神イザナギと祀り上げられ、その木、ノスタルギガンテスと命名された木もまた、美術品として祀り上げられていく。
「ノスタルギガンテス2」の公演の後、演出家の丹下一氏がアフタートークで話していたが、この本を映像にすることはとても難しく、芝居でならば表現できるのではないかと舞台化してみたのだとか。確かに、読者が作り上げるこの本「ノスタルギガンテス」のイメージは千差万別だろう。登場人物の独特なイメージやキップルが増殖していく不気味なイメージや作品全体が持つ恐ろしさも映像にするのは難しい。何より、寮美千子さんの言葉によって限りなく無限に作り上げられるこの何とも表現しがたい残酷なまでに暗いイメージをスクリーンや舞台という限られた平面や空間で表現するのは、無理がある。まあ、どんな小説でも物語でも、原作を読んだあとで映画を見た時にがっかりすることが多いのだから、それは仕方がないことかもしれない。
けれども、舞台の上では、物語の中の言葉が活字で読んだ時とは違って、強く感じられた。文字で読むだけでは感じられない言葉のリズムが、トランペットの音と合わさって、主人公の櫂の感じる不安が観客へ本を読む以上に伝わってきたように思う。『ノスタルギガンテス』の作者、寮美千子さんは童話、絵本、小説、ノンフィクション、詩と幅広い作品を書いている。読み聞かせをしても、詩人の書いた絵本を読むときは、子どもたちがよく耳を傾けてくれるが、『ノスタルギガンテス』も、その詩的な文章が、役者の声を通して強く伝わってきたのだと思う。
その詩人としての寮美千子さんが、奈良少年刑務所の社会性涵養プログラムの講師をしている時に子どもたちから生まれた詩を編んだ本『空が青いから白をえらんだのです―奈良少年刑務所詩集―』(新潮文庫 右→)がある。社会性涵養プログラムとは、刑務所のなかでも、みんなと歩調を合わせるのが難しく、いじめの対象にもなりかねない子どもたちに対し、SST、絵画、童話と詩の授業をそれぞれ月1回、1時間半の授業を6カ月行うというもの。SSTは挨拶の仕方や嫌なことを頼まれたときの失礼のない断り方など、基本的なコミュニュケーションの方法を学ぶ授業。絵画は対象をきちんと見つめて写生することで、解放された無心な時間をすごす時間。そして寮美千子さんが担当した童話と詩の授業では、絵本を題材にお芝居のように朗読したり、詩を読んだり、最後には彼ら自身が詩を書いて自分を表現する。そこで書かれた詩が、この本の中に載っているのだ。
私は、この本を一気に読み終えた。読み終えて、しばらくは他のことは何も考えられなかった。子どもたちの詩を読んで、凶悪な罪を犯した受刑者の心の中に、こんなにも柔らかなものがあるのか、そして人は変わり得るものなのかという思いでいっぱいで。ぜひ、多くの人にこの本を読んでもらい、犯罪のない社会を作るには何が必要なのかを考え、議論してもらいたいと思う。
ところで、寮美千子さんが行った社会性涵養プログラムの授業で、子どもたちの心を開くために、童謡に合わせて動いてみたり、絵本の登場人物を演じたりするのだが、これらがこんなにも子どもの心を開くものなのだということに驚いた。私も子どもたちが英語で歌ったり踊ったり演じる活動を行う教室を主宰しているが、時に子どもたちが心を開いてくれていると感じることがある。だが、それはいいグループが形成されている時のこと。少ない人数のクラスやまだ子ども同士がなじんでいなかったりすると何をやってもうまくいかない。寮さんも言っているが、心を開くには「場の力」「座の力」が必要なのだ。
話は変わって、「ノスタルギガンテス2」の少し前、石巻市民劇団夢まき座による「100万回生きたねこ」(佐野洋子 原作)の公演があった。私もお手伝いをしていたのだが、お年寄りから子どもまで幅広い年齢層の観客が集まった。公演から2カ月ぐらいたったある日、私が子どもセンターで行われるイベントのために蔵書を読んでいると、小学生の男の子が5,6人、本棚のところにやってきた。私が本を読んでいるのを見て「ぼくも本、読もう」と言って彼らはマンガ本を読み始めた。けれども、まだ一文字ずつ拾って声にだしてようやく読めるぐらいの読解力の子どもたち。意味が分からず、みんなマンガ本を放り投げた。けれど、一人の子が「あっ、『100万回生きたねこ』だ。おれ、お芝居で観たんだ」と言って本棚から絵本を取り出し、たどたどしい様子で声に出して読み始めた。すると、マンガ本を放り投げた男の子たちも絵本の周りに集まってきた。彼らは、読み終わった後でどんな感想をもつのだろう、興味津々の私はそっと横で様子を窺っていると、そろそろ小学生は帰りましょうというアナウンスが館内に流れ始めた。それでも、彼らは読んでいたのだが、残念ながら最後までいかないうちに時間切れ。家に帰っていった。
2カ月たっても舞台の印象は強く残っていたのだろう。芝居という場では、原作となった物語を知りたいという力でも生まれるのだろうか。かくいう私も「ノスタルギガンテス2」を見た後、原作を読んだではないか。子どもたちが本を手に取って読書に向かうことが難しい現代、芸術に触れるだけでなく、舞台でイメージを作ってもらうことで子どもたちが本を手に取ることが楽になるのなら、もっともっと手軽に芝居を観ることができる世の中になれば、読書人口も増えるのだろうな。
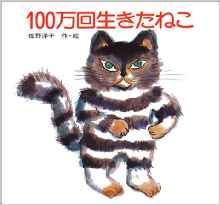
㊧『100万回生きたねこ』
佐野洋子 作・絵/講談社
初版は1977年。30年以上も読み継がれてきた絵本。