
2015年8月30日 発行
暑い暑いと言っていたら、あっという間に朝晩は上着のお世話にならなければならないぐらいに。今年は例年以上に8月の1カ月間の気温の落差が激しい。これらは、地球温暖化の影響という人がいたり、いや本来は地球がこれから氷河期のように寒くなる周期に入るのだから温暖化はないという学者がいたり…。いずれにせよ、やさしい生活をしなきゃ地球からしっぺ返しが来るんだろうなと思いながら、急な気温の変化についていけなくて鼻炎薬を飲む私。まずは自分の体にやさしい生活をしないと・・・。
■山登りとお花畑
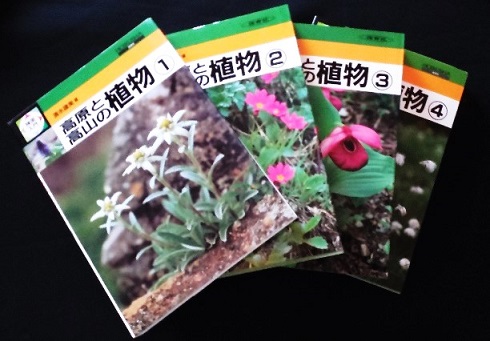
『検索入門 高原と高山の植物①〜④』
清水建美 保育社
検索入門シリーズとしては、他に樹木や野草・鳥・魚・岩石・星座などもある。 同じ保育社刊の原色図鑑シリーズは、学校図書館などで必ず見かける図鑑。
今年の夏は生まれて初めて北海道に行ってきた。と言っても観光ではなく、自分の教室の子どもたちの引率で。ラボ教育センター主催の3泊4日のサマーキャンプは、例年、蔵王で行われるのだが、今年は蔵王山噴火の可能性で中止になったので、思い切って小学生たちと北海道のニセコで行われるキャンプに行ってきたのだ。
ニセコ町のホームページによれば、ニセコ町は、道央の西部、後志管内のほぼ中央に位置し、札幌市や千歳空港から自家用車で約120分、小樽市からは自家用車で90分ぐらいのところらしい。私たちも新千歳空港でバスに乗って、ちょっとアメリカ中部の田園地帯を思い出させるような農家の建物やトウモロコシやジャガイモの畑をぬけて、さらに信州の山の中のようなすがすがしい森を眺めながら、休憩も交えて3時間弱ぐらいで宿舎についた。
そして、キャンプ二日目、私も小学生勇士たちといっしょに国定公園ニセコアンヌプリ(1,309m)登頂に挑戦。久しぶりに履いたトレッキングシューズ紐をしっかり締め、ガイドの中川さんの指導の下、子どもたちの足手まといにならないように気合を入れて出発。
アンヌプリ登頂を目指す子どもたちは、ほとんどが山登りは初めてらしい。都会や町で暮らしている小学生たち、ぬかるんだ道や大きな石があるデコボコ道に悪戦苦闘。すでに4分の1ぐらい登ったところで、「辛いよ」と訴える子たちが出てきた。慣れないトレッキングシューズを上手く履けずに足が痛くなる子も。いっしょに登った高校生や大学生がそんな小学生の様子をガイドの中川さんに伝えるたびに、中川さんは「集団で登る時は一番ペースの遅い子を列の前方で歩かせてその子にあわせるんだよ」とか、「靴はかかとをしっかり合わせて、紐は一番上までしっかり締めるんだよ」などと丁寧に指導。高校生や大学生にとってもいい勉強だ。
こんな様子なので、山登りなんて?十年ぶりという私も、このペースなら無理なくみんなについていける。見れば、道端は黄色や白い花々が咲き乱れるお花畑状態。うれしくなった私、子どもたちに「ねえ、黄色いきれいな花がたくさん咲いてるよ」と声をかけるが、子どもたちは全く反応なし。『ふしぎの国のアリス』の芋虫が乗っかっていそうな真っ赤な大きなキノコなんかもあって、「見て!見て!」と連呼すれば、ようやく「あっ、そう」という感じ。みんな、山道を歩くのに必死で周りに目がいかないようだ。こんなにきれいな山道には、そう滅多にお目にかかれないのに。
途中の休憩で、ガイドの中川さんに「たくさんお花が咲いていますね。アキノキリンソウですか?」と聞くと、「正確にはミヤマアキノキリンソウですが」と丁寧に訂正。確か、ミヤマアキノキリンソウは高山植物図鑑に載っているような植物で、本州では小学生が遠足やキャンプで手軽に登れるような山では見られないはず。聞けば、アンヌプリは学校登山で利用されることの多い山だそうだが、北海道では、1,000m級の山でも亜高山帯や高山帯の植物がみられるのだとか。そうか、バカな私は北海道は北国なのだということを忘れていた。事実、しばらく登るとダケカンバやハイマツが茂る高山帯の景色があらわれた。山頂が見えてくると子どもたちも俄然元気になる。辛いと言っていた子どもたちも何とか山頂まで登り切った。
さて、キャンプから帰ってデジカメの写真をパソコンに取り込みながらアンヌプリで撮った花々の写真を見ると、中川さんから植物の名前を聞いたはずなのに全然思い出せない。そこで、本棚の奥から図鑑『検索入門・高原と高山の植物①〜④』(清水建美/保育社)を久ぶりに出してみた。大学の卒業論文の指導をしていただいたのが著者の清水建美先生で、研究室に入ったときに先生からいただいたものだ。あの頃は、いつもこの図鑑を持ち歩いていたものだ。先生と北陸の白山に登った時もこの4冊の図鑑をリュックに入れて持っていたら、いっしょに登っていた先輩に「何をわざわざそんな重いもの持ってきて。清水先生といっしょだったら図鑑いらないでしょ」と笑われたこともあったっけ。
図鑑を開くと、たくさん書き込みがある。あの頃は、山に登ると聞いた植物の名を小さなフィールドノートに書き込み、家に帰ると図鑑で調べて見た日付や場所などを書き込んでいた。なんだか懐かしい。今は、植物とは縁のない仕事なのだが、それでも学校で読み聞かせのボランティアをする時もついつい植物に関する絵本などに手を伸ばしてしまうのは、あの頃の名残なのかもしれない。
『やさいばたけははなばたけ』(広野多珂子作・絵/佼成出版社)は子どもたちに身近な野菜の花を描いた本だ。この本に描かれた花を「これ何の花かわかる?」とクイズ形式で聞くと、石巻のような田園風景の中で育った子どもたちでも答えられないので面白い。「ジャガイモに花咲くの?」なんていう子もいるし、隣のページのトマトの花を見せて同じナスの仲間(ナス科)なんだよというとさらに驚かれたりする。
さらに同じ広野多珂子さんの絵の『あめだからあえる』(さとうち藍文・広野多珂子絵/福音館書店)も雨が降る日によく読み聞かせに持って行く。
こんなふうに科学絵本はすてきなものがたくさんあるのだが、先日、改めて考えさせられることがあった。それは、NHKラジオで夏休みこども科学相談という番組があって、この番組、私は子どもたちの本質をついた質問にしどろもどろする科学者の先生方の受け答えが面白いなあと思いながらいつも聞いているのだが、そこでの先生と子どもの受け答えを聞いていた時のこと。先生が「何を見てそう思ったの?」と聞くと、「絵本に書いてあったから」と子ども。「じゃあ、○○ちゃんは、本物を見たことあるの?」「ううん、見たことない」。こういう答えをした子どもが一人じゃなかったのだ。
科学的な知識を広げてくれる科学絵本だが、残念なことに、読むだけで子どもたちは満足してしまっているのではないか。ちょうど、ネットで調べて、知っているつもりになっているのと同じように。いや、それだけでない。今は、親も子も忙しい。忙しいなら、実物を見るより絵の方が簡単だ。事実、私も学校に畑に咲いた本物のジャガイモの花でなく、絵本を持って行くじゃないか…。 恩師の清水先生は、図鑑を私にくださっただけでなく、私に先生の調査研究に同行する機会をたくさん用意してくださったり、私の論文のためにフィールド出る時間を割いてくださったりした。4冊の図鑑をとおして、天国から先生が今の子どもたちにとって何が必要かを改めて考えろと言ってくださっているような気がする。
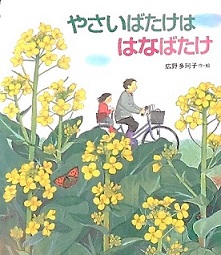
『やさいばたけははなばたけ』
広野多珂子作・絵
佼成出版社
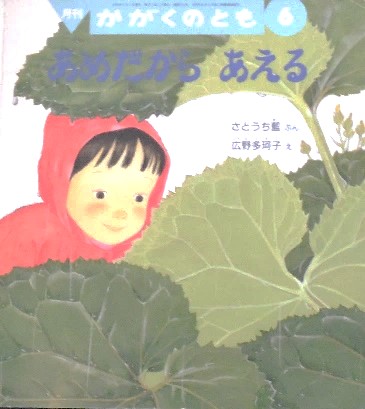
『あめだからあえる』
さとうち藍文・広野多珂子絵
福音館書店
Copyright (c) Yoda Harumi, 2015, All Rights Reserved.