
2015年6月24日 発行
筆者、依田が勝手に毎月1回の発行していたこの通信。3人の子育ての忙しさと雑事に追われ、発行を2年ぐらい休みますと宣言して、気が付けば早14年。再開を待っていた方、ごめんなさい。この14年間で、私の執筆の原動力である我が子はほぼ巣立ってしまったが、幸い職を得て、子どもと接したり、子育て真最中の父母と絵本や物語について話しあったりする機会もできた。だが、相変わらず話下手な私。伝えたい思いの半分も伝わらないことも多い。七夕の短冊に願いを書くと叶うという。この通信を七夕の笹にぶら下げたら、私の思いもとどくかしら…。
■マザーグースは楽しいぞ!
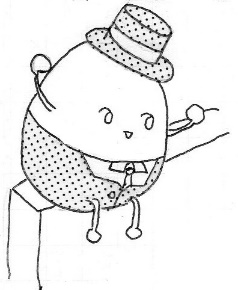
私は、3番目の子どもが幼稚園の年長組に通いだした頃から、ラボ教育センターが展開するラボ・パーティという教室のテューターという仕事をしている。テューターって何?と名刺を配るたびに言われるが、やっている仕事は子どもたちが主体的に英語で物語劇を作り上げていくお手伝い。先生でもないし、演出家でもないし、かといって出演者でもない。だから、テューターtutorと言うらしい。日本では馴染みのない仕事だが、アメリカではTutor of Labo Partyというと納得してもらえるので、何?と変な顔をされるのは、日本にそういう立ち位置の仕事がなかっただけなのだと思う。
そのラボ・パーティ、全国に0歳〜大人まで会員がいる。私は、幼い子どもたちには必ず、マザーグース(ナーサリーライム)にふれあってもらうようにしている。
マザーグースとは、英語圏の子どもたちの間で古くから伝承されてきたわらべうたのことです。イギリスではナーサリーライム(Nursery Rhymes)と呼ばれています。うただけでなく早口言葉、なぞなぞ、昔ながらのイギリスの風俗、習慣を伝えるもの、ナンセンスなものなど様々な種類があります。
ラボ教育センター「『おはよう』から『おやすみ』まで 親子で楽しむマザーグース」より引用
要するに、マザーグースとは、英語圏のわらべうたのことだ。だが、マザーグースという言い方は必ずしも一般的でないようで、イギリスではナーサリーライムと呼び、マザーグースはかなり狭い意味でしか用いられていないらしい。(
参考:鷲津名都江『わらべうたとナーサリーライム―日本語と英語の比較言語リズム考』晩聲社)
とにかく、子どもが長い物語を楽しめるようになるためには、まず、わらべうたが口ずさめるようになり、その後に「いないいないばあ」(文:松谷みよ子/絵:瀬川康男/童心社)のような、起承転結の起と結で終わるようなごく短いストーリーが繰り返された絵本が楽しめるようになって、その後ようやく起承転結のある長い物語が楽しめるようになるらしい。英語を日本語と同じ道筋で楽しめるようになって欲しいと思うならば、やっぱり最初はマザーグースということになる。
私自身のマザーグースの思い出といえば、高校の英語読解の教科書に”Humpty Dumpty”のうたの歌詞が載っていて、読み終わった先生が、ハンプティダンプティの正体は卵であるという解説をしていたことと、大学の教養科目のやはり英語読解のテキストにライムと解説が書いてあり、先生が厳めしい顔で解説していたこと。何のことやらさっぱりわからず、右の耳から左の耳に抜けていったっけ。
例えば、日本のわらべうたにしても、じっと椅子に座って「はないちもんめ」や「あんたがたどこさ」の歌詞を読んだって面白くない。声に出して歌って遊ぶことで、韻を踏んでいることもわかるし、覚えることだってできる。やはり、マザーグースも歌って遊んで、初めて身になるのだと思う。
しかし、子どもたちにマザーグースで遊んでもらうのは、意外と難しい。遊ぶには人数や場所が必要だ。「ロンドン橋おちた」だって、橋の下を通る人が1人や2人じゃ面白くないし、鬼ごっこをするにも、ある程度広い安全な場所がいる。だったら、手遊びや大人の膝などに乗って楽しんだりするうたで遊べばいいじゃないかと思うが、これには最大の難関が残っている。それは、大人がマザーグースを歌えないと幼い子どもを遊ばせられないということ。
幼い子どもはすぐに歌えるようになるマザーグース。けれど、成長するにしたがって歌えるようになるには時間がかかり、大人にとっては、大変な作業となる。かく言う私も、車の中でCDを聞き、iPhoneに入れて電車バスでの移動の時にイヤホンで聞き、お風呂やトイレで何回も口ずさんで必死で覚える。すると、こっちが覚える前に、後部座席にいる我が子が先に覚えて歌っていたりする。
ところで、アメリカのオハイオ州に行ったときのこと、ホストファミリーが通う教会のメンバーのお嬢さんが間もなく出産を控えているといので、私もいっしょにベビーシャワーに参加させてもらった。ベビーシャワーというのは、妊婦さんが妊娠8ヶ月ぐらいの安定期に行われる参加者女性限定のアメリカのお祝いの行事で、妊婦や妊婦の家族の友人たちが集まり、みんなで出産や子育てのアドバイスをしたり、出産祝いを持参したりするパーティである。その時も、サプライズで紙おむつのケーキが用意されていたり、みんなで妊婦さんのおなか周りの長さを当てあったり、目隠しをして人形におむつをあてるゲームをしながら「男の子はおむつをとるとき気をつけないとね。噴き出すからね。」などと年輩のご婦人方が和やかに笑いあふれるアドバイスをしたり…。そして、「これは、お母さんになるのに大切なことよ。全部解けないとね。」と言って配られた紙には、ずらりと並んだマザーグースに関わるクイズの数々!
果たして、私たち日本人はどれだけ日本のわらべうたを大切にしているだろう。マザーグースの中にEeny,meeny,miny,moと鬼を決めたり、何かを選んだりするときに唱えるライムがあるが、教室の子どもたちに「この歌と同じように使う日本語のうた知ってる?」と問いかけてみた。すると、我が子も含め兄弟姉妹であってもみんな少しずつ違う歌を歌ってくれた。どうやら違いは、学年や保育園、幼稚園の違いによるものらしい。本来親から子へと伝承されていくはずのわらべうたが、日本では、幼稚園や保育園、学校の先生から伝えられているのだ。私たち大人は、若い世代の日本語力が低下していると嘆く前に、もっとすべきことがあるということではないだろうか。
■私の本棚…最近読んだ絵本の覚書
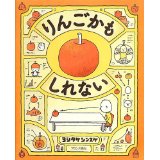
りんごかもしれない
ヨシタケシンスケ作
ブロンズ新社
朝は子どもたちにさっさと支度して、学校に行ってほしい。でも我が家の子どもたちは、テレビが点いていると(それがニュース番組でも)画面に釘付けになり動きが止まってしまう。おかげで、遅刻寸前で学校に行くことに。困ったな、何か対策がないかなと考えて思いついたのは、テレビを消し天気予報やニュースは、ラジオで聞くこと。この方法、子どもたちの朝の支度がスムーズになっただけでなく、絵本や小説の作家のお話が聞けるおまけまでついてきた。
この本は朝のNHKラジオに作者のヨシタケシンスケさんが出演されていて思わず購入。お笑いコンビ麒麟の川島明が絶賛していた。小学生にうけるかなと思ったが、意外にも高2の娘のお気に入りに。難しい英文や数学の問題に頭悩ませている高校生は、このクスッとくる笑いに癒されるのかな。
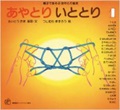
あやとりいととり1〜3―親子であそぶあやとり絵本
親子で遊ぶあやとり絵本
さいとうたま著
つじむらますろう (イラスト)
福音館書店
Ring on a stringという英語の歌でゲームをしようと思ったが、ゲームをするには子どもの数が足りない。せめて、stringつながりで遊べるものは?と思いついたのがあやとり。慣れていないと、小学4年生でも糸を思いどおりに操るのは難しいようで、本を見てもなかなかできず、私が「はい、こっちの糸取って、ここを放して…」と何度も繰り返すことに。
先日裏方のお手伝いをした音楽イベントで、合唱の先生が、ため息交じりにボソリ、「子どもを指導するのは大変だ。大人と違って何度も何度も繰り返さないと…」と。何事も子どもに教えるのは大変なのですね。